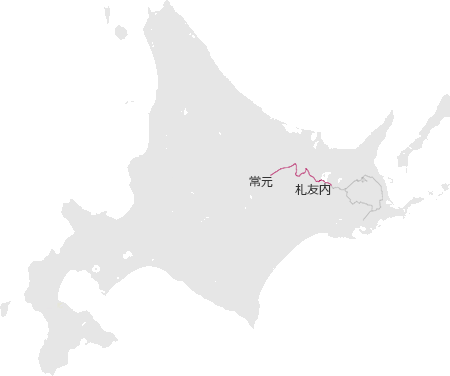
札友内→ウランコシ
(以上#4-1)
(以下#4-2)
→津別峠展望台
(以上#4-2)
(以下#4-3)
→津別
(以上#4-3)
(以下#4-4)
→チミケップ湖
(以上#4-4)
(以下#4-5)
→チミケップ湖
(以上#4-5)
(以下#4-6)
→訓子府
(以上#4-6)
(以下#4-7)
→常元
133km
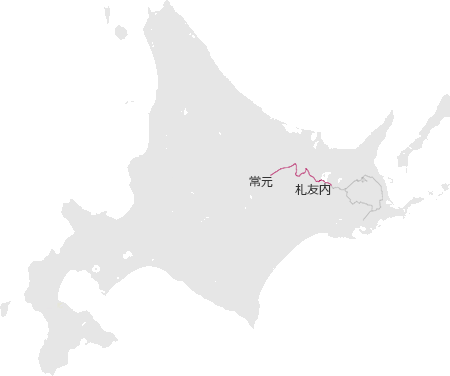
|
|
|
4時。もう朝か、と思いながら起床。起きると身体も気持ちもしゃきっとするのは大変良い傾向だ。
裏手の森で葉っぱに水滴のような音がしている。しかしそれが雨な訳が無いと思っていた。天気予報は曇りか晴れ、終日降水量0mmのみならず降水確率0%。すっかり津別峠に向かう気になれている。
しかし、天気が悪い場合は不可抗力とし、今日の行程が津別峠経由じゃなくて美幌峠経由になるのは仕方無い、という気もしている。過去にそういうことはあった。もっと言えば、走らずに列車で輪行という選択肢もある。その場合も弟子屈に6時過ぎに着いて輪行を始める必要はある。どれも現地次第の定めとして悪あがきせず受け入れるべきだが、どの選択肢も出発する必要はある。などと思いながら出発に向け黙々着々と準備を進め、5時に屋外に出ることができた。順調だ。
果たして宿の外は全く雨が降っていない。水滴の音は相変わらず続いている。それは森の葉っぱに着いた夜露が落ちる音のようだった。何の音でもいい、雨が降っていなくて熊が出なければ。全く問題無く、津別峠確定だ。
自転車に荷物を積み、身体に日焼け止めを塗ったくり、更にムシペールを速攻で塗らねば。釧路川岸の森の中だけあり、油断すると蚊に刺されるのだ。速攻でムシペールを塗ったつもりが、脛辺りが痒いということは、早くもやられてしまったようだった。
5:25、鱒や発。

 ■
■
札友内の牧草地には、視界100mぐらいのけっこうな濃霧が漂っている。景色は全く見えない。牧草地のはずだったのが、いつの間にか釧路川沿いの森に入っているようだった。この辺り、何故か調子が乗って以前30km/hぐらいで常に走れたような気がする。今のところ25km/hぐらいで推移しているので、以前よりペースが落ちているのだろう。歳だなとは思うが、でも歳なのも意外に悪くないというのは本当の話だ。それに歳は不可抗力で誰にもやって来る。






屈斜路の湖岸縁を乗りこえ、屈斜路湖湖岸区間へ。霧が濃く景色の雰囲気はややどんより気味だし、そもそも道の行く手からして遠くまで見えない。にも拘わらず独特ののんびりした雰囲気が、国道243の路上空間には感じられる。早朝で車がいないからというだけじゃない。国道としては落ち着ける良い道だと思う。しかし、美幌峠の国道243より津別峠・上里の道道588の方が、やはり圧倒的に静かで私的には好ましいとも思う。すみません気が多くて。いつか罰が当たるね。















6:10、ウランコシ着。
道道588分岐に近づくと、車がどどっと数台降りてきた。驚いた。この早朝に、あの静かな国道545から車が続けて数台も。過去の訪問ではあり得ないことだ。でも理由は想像できる。おそらく、近年有名になっている津別峠展望台の雲海を見に来たのだろう。あれだけ車が続けて降りてきたら、森の熊は奥に引っ込んでくれるかもしれない。そういう点では有り難く心強い。



気温が低いせいか、道道588の直登区間でもその先森に入るまでも記憶より短く感じられた。森までは頭上が開けているので、この区間で陽差しが出ていないと随分楽なのかもしれない。それでも斜度は8%ぐらい。森に入る頃には既に汗だらだらになっていた。
 ■
■


森に入っても斜度は厳しい。でも、ギヤを下げて落ちついて登ればいつもの坂であり、こちらが汗だらだらでも森の中のひんやりした空気は記憶通りだ。


 ■
■

しばらく8〜9%で安定していた登り斜度は、少し登ると沢渡り部分や交換部で緩くなり、緩急が付き始める。これが気持ち上だいぶ助かる。。






そして標高が400mを越えると、森が開け始め、森の中から俄然涼しい風が通るようになる。道が貼り付く斜面の傾斜がより険しくなるため、木々がまばらになるせいだろうと思われる。この涼しい風も、毎回身体を随分楽にしてくれる。以前はこの辺から斜度が緩くなるように思っていたが、最近はもう斜度が少しも変わっていないことをプロフィールマップで見て知っている。まあ、全体的に地道にこつこつ登っていると、人生報われるものなのだ。いやいやいや、登れば登るほど厳しく際限無い峠も多いよ、等と思い直すのももう毎度の事。楽しい津別峠訪問なのだ。





木々がまばらになった辺りから、頭上の霧が晴れてきた。そして森の中に、曇りとは明らかに違うニュアンスの明るい光が射している。天気予報通りの展開だ。こうなると晴れに向けてもう期待満々である。下の方は雲が溜まっていて何も見えない。今日の津別峠展望台は、晴れの雲海の景色を期待していいかもしれない。





標高550m〜600mには、かつて2年ぐらい津別峠を通行止めにしていた崩落を復旧した箇所がある。斜面の木々が崩落通りに剥ぎ取られていて、つづら折れの下側の道から上側を見通せる、津別峠では珍しい場所だ。今日は全体的に見通しが良いので、上と下の位置関係がよく見える。屈斜路湖側は相変わらず霧の中だが、空には青い部分が見え始めている。登ってゆくにつれ、明らかに晴れてきているのだ。


つづら折れで折り返した道が、山肌と峰部分を巻いてゆく。この辺で峠まで標高差100m。特に終盤は斜度が上がり、なかなか津別峠に着いてくれない。しかし今日は完全に雲の上に出たようだ。空は真っ青、陽差しは暑いものの標高が上がって暑さは全体的にだいぶ和らいでいて、緑の鮮やかさが登りを助けてくれる。森が言葉にならない何かで語りかけてくれるような気にさせられるのだ。







8:00、津別峠着。これで今回も津別峠に来れた。水を飲んでクロワッサンをふたつ腹に押し込み、よし、そのまま行ける。必要以上に休むこと無くそのままふるさと林道区間へ。全体的に30第40台の頃よりペースは遅くなっているものの、この一連の流れが懐かしく嬉しい。



ふるさと林道は流石の斜度10%以上、斜面を巻いてゆく登りは眺めからしてかなり厳しい。こちらもそんなことはわかっている。ここまで温存しておいたインナーローを投入、一気に脚の負担が下がるのが有り難い。





途中までいつもより苦しくなく、淡々と登れているなと思っていた。ペースが良いのかもしれない。こりゃ久々の30分かなとも思った。しかし峰を巻いて次の直登区間で、GPSの電池が切れた。有り難く脚を停め、フロントバッグから電池ケースを出し、交換して再起動。すぐ時間が経つ。まあしかし、これが無くても35分かかっただろうな。



何はともあれ、毎回、直前の根釧台地202kmコースで開陽台への登りを押したことへの引け目が解消される登りである。今回もここ登れたなおれは、という。これで今年後半も頑張れるのだ。


展望台駐車場への一登り、最後の13%はやはりかなり厳しい。8:40、展望台到着。今年もここまで登れた、と脚を着いて眺める展望台は、一面の青空をバックに眩しい陽差しの中、相変わらず空に少し突き出るように建っているのであった。
自転車は駐車場から上に上げてはいけないのは、去年と同じである。折角来たのに。従うけど4サイドならOKとかにしてくれよ、等とも思う。そして今回目新しいのは、展望台に入る扉の鍵が掛かっていることだ。開くのは9時という表示もある。年々何かと決まり事が厳しくなっているのは、津別峠が雲海で賑わっていることの証しかもしれない。かならず何かをしでかす輩がいるんだろう。
9時まで20分。待とうかどうしようか。ガスで何も見えない年など、15分ぐらいで撤収してしまうのだ。まあしかし、時間はどうあれやれることから始めておこう。とりあえず展望台下の広場で、雲に埋め尽くされた屈斜路湖側の写真を撮りはじめた。ここ数年、屈斜路湖側は毎回視界20〜数10m程度だったのが、今年は随分落ち込んだところから雲海になっている。雲海の向こうに西別岳か何かが頭を出しているのが大変嬉しい。
そのうち管理係さんらしき人が中から鍵を開けたり閉めたりし始めた。時間を見るとあっという間に10分経っていてもう8:50。9時まで待つことにした。
展望台の一番上に登っても、屈斜路湖が雲で埋め尽くされていることには変わり無い。しかし、やはりその眺めは格別だ。
まずは東側。本来屈斜路湖が拡がっているはずの眼下には、雲がたぷたぷ溜まっている。その向こうには、屈斜路湖外周の山々が頭だけ出している。更にその先、知床方面の山々がひときわ高く、奥へと続いている。野上峠を越えた斜里方面は晴れ渡っていて、平野部がよく見える。反対の西側は全く雲が無いので、外輪山に囲まれた真っ青な屈斜路湖の眺めを知る者としては、眼前の風景に雲が無い屈斜路湖を想像してしまう。しかし今の雲海も、これはこれで2022年の津別峠展望台と屈斜路湖そのものなのだ。
一方、南側から西、北側へぐるっと見渡す阿寒方面や津別方面にはほとんど雲が無い。雄阿寒や雌阿寒の起伏や岩肌がくっきりと、のみならず大雪がシルエットだけじゃなくうっすらディティールまで見えるのはこれまでの訪問中初めてじゃないかと思う。以前津別峠展望台から初めて大雪を意識したのはいつだったか、もうすっかり忘れてしまっている(2010年だった)。雨で訪問を断念したり崩落で道道588が通行止めだったり、来れてもガスで景色が全く見れなかったり。思えばこの眺めに再び会えた今日まで長い年月だった。つい雲海に歓声を上げているて廻りの方に話しかけてしまう。
できればずっと眺めていたい風景だ。でも、2〜3分も眺めていればあとは同じ、再び眺められたことそのものに大変満足できている。ここまでやってきてこの風景に会えた、それでいい。もう次の場所に向かうのには悔いは無い。そういう一連の、毎度の流れ全部を自分がまた今年も味わえたことに、もう感謝しかない。




























9:20、展望台発。この山深い場所から1時間後にはもう津別の町中に降りてしまっているのだ。毎回信じられないことではあるものの、それをやっている。
さっき登ってきたばかりのふるさと林道区間をあっと言う間に道道588分岐へ。その後は山肌を巻いて高度を下げてゆく。見渡す山々は降りてゆくとともに近くの山肌になり、廻りの木々が密になって周囲の眺めが無くなった。そして谷間正面に見上げていた稜線部も谷間区間では見えなくなって、くねくねと急降下してゆく。




















山腹の森から上里に谷間に下りきって峠区間が終了。道道588は引き続き谷間のカラマツの森を下り始める。やはり山肌区間から降りてきて暑くはあるが、いつもほど暑くなっていないように思われる。いや、これが津別まで面白いように暑くなるんだよなと警戒し、上里で農家が現れた辺りからもあまり脚を回してペースを上げること無く、とにかく楽に下るままに下ってゆく。









しかし、谷間一面に畑が拡がる美都を過ぎ、更に下って津別の営みが行く手に伺えるようになってきた豊永辺りでも、警戒しているほどには暑くなっていない。この晴れにしては。というより、これは天気予報通りの状態、最高気温27℃という状態そのものであるように思える。













10:20、津別セイコーマート着。津別峠でも展望台でも食べているので、まだ腹は減ってない。とりあえずアイスに缶コーヒーで身体を冷やし、食糧のパンは不足しないように仕入れておく。
空に雲が増えてきているものの、日向側の店の軒先から影になっている裏手へ避難が必要な程、暑い。やはり津別は暑いのだ。でも、過去の津別での暑さでは全然ましな方だ。走るのに全く問題無い。
行けるかどうか心配だったチミケップ湖、これなら行けるんじゃあないのか。じゃ行こう。
10:55、津別発。国道241で本岐へ8km。津別で増え始めていた雲は休憩中に増え、空は薄曇りからもう少し厚め低めの雲に覆われるようになっていた。チミケップ湖もこんな感じかもしれない。まあしかし、このまま行ってみましょう。



風が無いのは大変有り難い。車が埃っぽいのが難儀する程度で、それは国道でいつものこと。今回はむしろ意外に少ない等と思うぐらいである。それでも、途中埃が目に入ってちょっと苦しんだ。



谷間左の山が意外に早く近づいてきた。8km、意外にあっという間だな等と思っていたら、道が山にぶつかってからが本岐まで意外に長いのであった。8kmは8kmである。



本岐で道道494へ。「訓子府方面通行止め」との看板が建っている。今年もチミケップ湖から先は道道682で最上・道道27経由なのか。まあ、現地でもう一度確認する必要があるな。



狭い谷間の森と茂みに埋もれるように、畑や牧草地が断続する。交通量、道幅とも、やはり気持ちがほどけるように落ちつく道だ。天気は相変わらず薄曇りであるものの、薄日が出たと思っていたら陽差しが差しはじめまた雲に隠れ、その陽差しの時間がどんどん増えている。




 ■
■
今日は津別峠の登りで涼しく展望台で晴れ、いつも暑い津別市街では薄曇り、そしてチミケップ湖へ向かうこの道で晴れつつある。横風気味の向かい風が多少強くなり始めてはいるが、かなり都合のいい、いや、虫が良い程の展開と言える。



陽差しが出てくると例によって笑っちゃう程急速に気温が上がるのだが、耐えられなくなる前に路上に涼しい木陰が現れるのが、道道494の決定的に良いところだ。川が近いのも、木陰の涼しさに一役買っているかも知れない。






途中で雲の多くはどこかに行ってしまった。天気は完全に晴れ基調である。当然日なたは段違いに暑い。

 ■
■
ダート区間に入ると、辺りはぐっと涼しくなった。本岐からここまでずっと、ひょっとして2010年以来の青空チミケップ湖に会えるのではないかと思いながら進んできた。それがいよいよ現実になりそうだ。これだけ晴れるのは、熱中症になってしまった2010年以来である。あの時はこの坂を登れなかったんだよな、と鹿鳴の滝手前の坂で思い出す。今日は全然余裕だ。まあインナー併用ではある。










12:35、チミケップ湖着。どう見ても木々の向こうに青空が見える。何度来ても会うことができなかった風景が、今目の前にある。晴れるとなればあきれるほどあっけらかんと、当たり前のように穏やかな天気だ。風も無いし、暑すぎるということも不穏な雲がどこかに盛り上がっているということもない。
道道682合流点の、いつも自転車を立てる場所には車が停まっていた。毎度の自転車撮影ポイントを前にやや残念だが、まあいい。この先のキャンプ場まで、いくらでも撮影ポイントはある。それより、木々の間から見える湖岸が本当に青い。青空を映しているのだ。今日は札友内からここまでやってきて、それなりに晴れが続いていて、それなりに暑い。だから今急に晴れた訳じゃなくて、朝から続いている当たり前の天気であるということに何の不思議も無い。しかし激晴れだった2010年以来、チミケップ湖に来る度に曇りか雨ばかり。今だから言ってしまえば、前回など曇りから現れた青空に大喜びしていたのに。こんな文句の無い晴天のチミケップ湖に会える日が、遂にやって来たのだ。

湖岸の道はいつも通りの極上ダートだ。それに加えて今日は、明るい木漏れ日きらきらに、森の向こうの青い湖面ちらちらで、風景が絶好調である。







車は多少目立つような気はする。でも、決して多くはない。熊出没の看板が立っているので、むしろ車の通行は安心できるというものだ。



まだお昼過ぎ、時間の心配は全く無い。安心感と満足しか無い。天国でダートをサイクリングする機会があれば、こんな感じの道なのかなとも思わせられる。




チミケップホテルの前を通過して更に奥のキャンプ場へ進んでゆく。いつも静かに鳴いているチッチゼミは、何故か今回声を聞くことができなかった。ここ以外で聞いた記憶があまり無いし、あれはピンポイントの季節のものなのかもしれない。





12:45、キャンプ場着。
道道494の訓子府方面分岐には、相変わらず通行止めの看板が立っていた。ここまでの標識通り、そしてここ何年かと同じ。この後は最上まで道道692・開成橋まで道道27経由、その後は北見盆地経由決定だ。
まあ、それは想定内ではある。それにしても「工事中のため通行止め」ではなく、「土砂崩落の危険のため通行止め」という看板を見ると、道道494訓子府方面はあまり積極的に通行止を解除しないような気もする。何年か前までチミケップ湖から出て行くのに好んで使っていた静かな良い道なので、やや残念な気がする。
等と思うのは一瞬。何はともあれ、キャンプ場から湖岸へ、青空の下眩しいくらいの草地に脚を進めてゆく。今日のキャンプ場はテントが多い。やはり過去の訪問で一番多いんじゃないかと思う。幸い、いつもの木陰ポジションには誰もいない。木陰の対角線反対にキャンプ客のご家族連れがシートを敷いていらっしゃるものの、この際私的指定席に自転車を置かせていただく。
晴れ、青空、夏の陽差し。打ち寄せる波は微風に吹かれて少しづつ変わってゆくようで、揺れる湖面の波は時々大きくなってまた静かになる。その間、大きなルリボシヤンマが空を悠然と、しかし素速く飛び回っている。羽音が時々ばちっと元気が良い。
2010年以来12年振り、快晴のチミケップ湖だ。12年間、今日まで北海道に来れている事がとても嬉しく有り難い。そして来ることができていれば、こんな年もいつかは来るのだ、とまた思った。
青い湖面に緑の草地の中で、心ゆくまで写真を撮って補給食などをのんびり食べ、気が付いたら1時間ぐらい経ちつつある。ずっとここにいれるならいたいけど、今日は札友内からやって来てこのあと置戸まで行く、というのが自分の旅なのである。この先も別の場所で新しい景色を楽しんで、また何時の日か再訪すればいい。こんな素敵な風景に会えた今回の旅、チミケップ湖の神様に感謝して先に進もう、という気になれた。
それにしても、さっき津別峠展望台でもちょっと思ったのは、お正月の気象神社の晴れお守りがかなり効いているんじゃあないかということだ。長年道東を訪問する度曇りや雨が続いたのに、今日はあまりに展開が都合良すぎる。
































キャンプ場で水を満タンにいただき、13:35、キャンプ場発。
道道682で最上の道道27までダートが6km。森の中には明るい木漏れ日が差していて、日なたの陽差しは結構鋭い。しかし森全体が涼しいので、1回半?ぐらいの丘越えを落ちついてのんびりゆっくり、それなりに時間は掛かるものの淡々とこなしてゆく。
ところで、等ともったい付けるぐらいに、木々の間からちらちら見えるその気配から目を背けていた。足下には木漏れ日が当たっているのに、これから向かう北見方面、いや、置戸方面の空が曇り始め、いつの間にかどんより真っ暗になっているのだ。雲の真下はどう見てもただごとでは済んでいなさそうだ。しかしあえて、今のところはあまり深刻に考えないことにしておく。考えたって雲が消えるわけじゃないしエスケープルートがある訳じゃないし、考えなかったら必ず雨に見舞われる訳でもない。気を揉むだけ無駄なことだ。




 ■
■


















ダートを抜け、更に下って14:20、最上で道道27に合流。開成峠はたったの登り80m。それでも登っている間はひたすら暑く、汗がだらだら出てきた。この間、空は雲っぽいものの意外に明るく、もう少し涼しくなって欲しいと心から思った程だった。









開成峠を越えると、今まで山影で見えなかった行く手の空が真っ黒になっていることを知った。頭上はそれでも明るい。などと思っていると大粒の雨が落ちてきて、やべっと思ったところですぐ止んだ。その後も空気中に大粒の水滴が舞ってはいたものの、それが雨には至らない位で推移し続けた。助かったのかもしれない。ただ、暗い空に向かって下り続ける間、路面は黒々ぬらぬらとものすごく濡れていた。所々の水たまりもかなり大きい。明らかにたった今、ゲリラ豪雨が通過した後なのだ。そして黒雲は向かって右側へ去りつつある。西から東に通過していったのだ。








14:45、開成橋着。チミケップ湖を13時半に出ても、やはりここまで1時間以上掛かるのだ。憶えておかねば。
道道27が開成橋で置戸川を渡る手前で、分岐する道道50へ。道道50は、置戸へと続く北見盆地南側段丘裾、外周部担当の道道である。この後置戸まで、極力田舎っぽい静かな道を意図してGPSトラックを描いている。その狙い通りに交通量はぐっと少ない。例年北見から留辺蘂へ向かうのに通らざるを得ない、ここから山一つ北の谷間を通っている国道35で、交通量にげんなりさせられることを思い出す。道は玉ねぎ、じゃがいも、とうきび等々、野菜畑の中に続く。八百屋やスーパーなどで見かける北見産の野菜達がこういう所で生産されているのだと思うと、より美味しく食べられるというものだ。こういう道なら、北見盆地も通っていて楽しいのだ。
開成橋近くでは豪雨が通過したばかりのように辺りはぬらぬら濡れていたが、その後すぐに路面が乾き、空は一旦晴れた。その後低くもりもりと勢いのいい雲が、次から次へとどんどん頭上を通過していた。



 ■
■










訓子府の手前辺りで、道が2010年に通った道であることに気が付いた。まあ計画段階でそうだとは思っていたが。通りやすそうな裏道を選ぶと、同じ道になってしまうのだ。



空には雲が増えてきていた。開成橋からそういう雲が増えたり減ったりする間に、雲の低さは次第に低くなっていて、一喜一憂しつつも何だかやばそうだな、とは思っていた。予想通り、置戸まであと10kmを切ったところで、遂に雨雲に捕まった。大粒のものすごい雨が急に滝のように降り始め、農家の車庫に避難させていただいたりした。まあしかし、こういう時は完全に雨が上がる前に走り始めないと、完全に雨が上がるのを待っていては時間が経つばかりでもあるのだ。
雨が弱くなって景色が澄み始めたタイミングをみて出発すると、案の上200mぐらい進んだところで雨はかなり弱くなり、残っていた最後の水滴も置戸の手前で完全に消えた。というより、置戸では路面が生乾きである。あまり降らなかったのかもしれない。そういう場所に人々が集まって住み、それが町になっているんだろう。
















 ■
■





16:30、置戸着。置戸コミュニティホールぽっぽは元置戸駅。池北線が廃止されて20年以上、元置戸駅と鉄道の記憶は未だに置戸という町で大切なものなのかもしれない。などと思いながら明日陸別まで乗る予定のバス停を確認し、目に入った置戸ハイヤーを明日の8時、今夜の宿の勝山温泉ゆぅゆから置戸ぽっぽまで予約しておく。勝山温泉ゆぅゆと置戸コミュニティホールぽっぽ、ネーミングに似た感性が感じられる。タクシーはOTHの前まで来てくれるとのこと、この時点ではそれがどういうことなのかよくわかっていない。有り難くお言葉にしたがうことにしておく。
また空が暗くなり始めている。もう宿まで10km、早く宿に向かって雨から避難せねば。






セイコーマートに寄って明日の朝食ネタを仕入れ、16:50、置戸発。町外れ、国道242拓殖橋交差点を過ぎたところで、頭上から行く手の空まで急に真っ暗になっているのに気が付いた。道端を見ると、ちょっと避難するのをためらう茂みの中に廃屋がある。しかしこれがこの先市街地で最後の軒下だな、と思ったところで、間もなく大粒の雨がぱらつき始めた。というより、100mぐらい先の空気にいつの間にか壁みたいな霞みが現れている。いや、それは大雨の壁なのだった。やべえ、すげえぞこれ、と思う間もなくそれが素速く近づき、そのまま辺りは土砂降りに包まれてしまった。この間20〜30秒。
速攻で雨具を着込み、予定コースの農道ではなく道道1050をそのまま先に進んでしまう。豪雨の中、向こうからやって来る対向車線の車が、あっという間にできた路上の水をかき分けワイパーが水を撥ね、通り過ぎてゆく。もう笑って脚を回しているしかない。
幸い豪雨は10分ぐらいで何とか止んでくれた。それでもまだ低い雨雲の下、薄暗い北見盆地の縁、静かな畑の中に道道88は続いていった。



 ■
■







雲は厚いものの少しは明るくなって雨が止み、谷間を挟む山が近づいてきて、勝山の交差点を過ぎると辺りが急に山っぽくなった。もう少し先で道道88はおもむろに山裾を登り始め、十勝へと向かってゆくのだ。
17:25、勝山温泉ゆぅゆ着。温浴施設であるゆぅゆには、道道1050〜88で置戸から芽登へ向かった時やその逆の時、何度か立ち寄って自販機やソフトに助けられた。その頃ゆぅゆには私が宿泊できそうな施設は無かったと記憶している。この辺りでは以前もう少し先の鹿の子温泉に泊まったり、10年ぐらい前には置戸の元冬季学生寮にも泊まった。北見地方・十勝地方の間は経路が限られてどこも距離が長い。北見側山裾の置戸、もっと言えば置戸市街よりもう少し山裾寄りのこの辺りに宿があると、計画上行程上重宝するのだ。自転車で道道88を越える場合限定の便利さではあるものの、まあしかし以前からそういうことを思っていた。
思いがあれこれ、ここに泊まる日が来たことは大変感慨深い。明日はここを出発して十勝に向かいたかった、と思う。ただ、今回一番の長丁場が運休になりほっとしていることも確かではある。



もともと温浴施設のゆぅゆ本棟に宿泊室は無く、ゆぅゆ敷地内にログハウスのバンガローが2棟建っている。しかし今回私が泊まるのは、OTHと名付けられた定員2人のトレーラーハウスだ。OTHとはOketoTrailerHouseの略とのこと。
フロントで受付を済ませ、鍵を貰ってOTHへ向かうと、2.25×5mぐらいのトレーラーハウスが4棟、芝生の中に置かれていた。というより据え付けられていた。トレーラーハウスの前まで舗装通路が設けられていて、タクシーに直付けしてもらえそうだ。
中へ入ると内装も家具も真新しく、空調はあるし水廻りはあるし自炊設備もある。ゆぅゆの温泉はもちろん利用でき、シャワールームまであるのでその気になればここだけで汗を落とすことも可能だ。来ないは有り難く温泉に行くつもりではある。つまり、室内は通常のホテルの部屋と変わらない。そして考えてみると、細長い部屋の形の外がまるっきり屋外なのは大変楽しい。ガラス戸の外にバルコニーが付いていて木製の机と椅子が置いてあるので、長居する場合はバーベキューできそうだ。
トレーラーの外側端部にはフックと、反対側には車両ナンバープレートが付いている。また、外から見ると水廻り部分に地面からコンクリートダクトというかシャフトが立上りで付いている。これらは明らかに建築確認申請回避のテクニックだ。建築確認申請というものはそれ程までに面倒であり、建築基準法はそれ程までに厳しいのである。そして建築確認申請をしない代わりに車両ナンバープレートが付いているのだ。
などということは今の私には全く関係無い。快適にここ勝山で一晩過ごせること、そのことがこよなく有り難い。自転車はこの際室内に入れてしまうことにした。これなら明日解体して、タクシーにOTHの前で載せるのに大変便利である。カーテンや絨毯を汚さないように注意しないと。
夕食はゆぅゆの食堂。メニューはまあ普通ではある。しかしツーリストが栄養をたっぷり補給して「美味しかった」とつぶやくのに何の不足も無い。美味しくお腹いっぱいになって、「結局おれは夕食を食って幸せになるために日中自転車で走るんだなあ」などと思いながら部屋に戻った。でも、それ以上何が要るのかと言われてもよくわからない。幸せなのは最高に素晴らしいことだと思う。









明日も楽しく走って南富良野に向かえると、更に有り難い。しかし天気予報を確認すると、午前中置戸町と足寄町で雨、輪行で通過する池田町と帯広市は曇りなのに、自転車行程としての経路の上士幌〜新得町ではお昼頃〜午後に雨。駄目押しで南富良野町で15時以降雨。つまり自転車での行程にすると、行く先々で通過時刻で雨になる。昨日の段階よりはましになっているものの、相変わらず最悪のパターンだ。
それでは、大手を振って休ませていただきましょう。輪行の接続も時刻も準備してある。
明後日は、南富良野町も美瑛町も午前中晴れ後曇りのようだ。むしろ明日休んでおき、久々の北落合とベベルイ基線に万全の体制で望むことができる。残念ながら、幾寅で毎回楽しみな美味しいなんぷカレーが、Webによると休止中とのこと。久しぶりの再会は叶えられなさそうだ。
記 2022/11/26
#4-2へ進む #4-1へ戻る 北海道Tour22 indexへ 北海道Tour indexへ 自転車ツーリングの記録へ Topへ