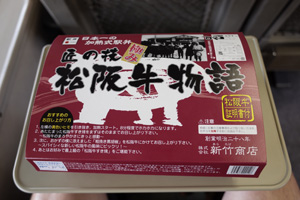
|

|
三瀬谷→宮川貯水池
(以上#1-1)
(以下#1-2)
→水呑峠
(以上#1-2)
(以下#1-3)
→上里→相賀
(以上#1-3)
(以下#1-4)
→クチスボダム→八幡トンネル
(以上#1-4)
(以下#1-5)
→坂本貯水池
(以上#1-5)
(以下#1-6)
→池原貯水池→上池原
121km
ルートラボ

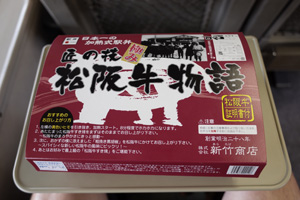
|

|
名古屋8:05発の南紀1号で9:47、三瀬谷着。私以外に降りた乗客は、大きなリュックを背負った人が10人ぐらい、普通の格好の人が2~3人。ハイカーの人々は大台ヶ原への登山客と思われる。大台ヶ原か。おれも行ったことはあるよ。行ったことだけは。
タクシー運ちゃんに水の場所やコンビニの場所を聞くが、あまり都合の良い回答は得られない。自販機のあるうちにおとなしく水を買っておく方が良さそうだ。
|
|
標高差550mの水呑峠に標高差540mの国道425八幡トンネル、坂本・池原貯水池経由で距離120km。夕食のタイミリミットは19時半頃、やはり18時~18時半には着きたい。普通に走れば全く不安は無いボリュームだ。ただ、余裕があるという訳ではなく、ちょっとした目論見違いがそのまま全体の狂いに直結する。そして距離と標高差だけじゃないコースの見込み違いは、紀伊半島の細道で当たり前の話だ。わかっているので一応そういう前提で行程を考えてはいる。でも余裕が少ない、そのこと自体がやはりちょっとした緊張に繋がっていた。
コース上の制限とは別に、水呑峠には13年振りの因縁がある。2005年4月29日。紀伊半島Tour05の初日、松阪から三瀬谷まで来ていながら、三瀬谷で撤退させられたのだ。この水呑峠を含む大杉谷全ての山が、前年の台風で入山禁止になっていたためだった。その後13年間、水呑峠の通行止めは1度も解除されなかった。時々水呑峠のその後をぐぐってはいたものの、調べて出てくるのは松阪土木事務所の通行止め情報と、途中で撤退したという訪問の記録ばかり。もともと通行が多いとは思えない道でもあり、てっきりこのまま廃道になると思っていた。
それが昨年末、この道は突如(としか言いようが無い)開通していた。今回私がそれを知ったのは4月上旬。この時点で、今年のGWツーリングは紀伊半島に決まったのだ。だから標高差550mとはいえ、水呑峠に問題無く向かえるというだけで、少々緊張していたのだ。
10:15、三瀬谷発。天気は晴れ時々曇り程度。紀勢本線北側、旧市街というか民家の間の、旧道というか普通っぽい細道を少し経由して県道31へ。



広めの川幅にたぷんたぷん、鮮やかな青緑の水面が特徴的な宮川とその谷間は、ゆったり大きく曲がりくねりつつ、瀬越えのような大したアップダウンも無く、比較的平坦なまま上流方面へ続く。切り立った山に囲まれて平地は狭いものの、全体的に谷間の空間にせせこましさは無く、大らかで開放的だ。集落は県道沿いやもう少し上の斜面、そして対岸にも点在しながら断続している。



今風に広めの道は、しばらくごく普通に対向1車線づつ。ところどころで道幅は多少狭くなってごく普通の県道っぽくなったり、更に狭くなって対面通行となった。拡幅工事が継続して少しづつ進行中ながら、あまり絶賛拡幅進行中という雰囲気でもない、緩めの県道である。




|
ルートラボのプロフィールマップでは、確か三瀬谷から宮川ダムの手前まで100mぐらいしか登らず、そこからダムまで一気に80mぐらい高度を上げ、ダム外周で平坦区間が続いてから最後に水呑峠へ向けて一気に登るということだった。今日の時間配分は、何しろまず宮川ダムの手前に辿り着いてからだという理解をしていた。このため、暑くもなく向かい風でもない、淡々と平坦な谷間の行程なのに、何となく気が急く気分になっていた。



県道13は江馬で道幅4~5m程度に細くなり、民家の低い軒が道に迫って続く、旧街道然とした表情の道となった。途端に気持ちが落ちついてきた。うん、ツーリングの道はこうじゃないとね。



11:00、天ヶ瀬着。まずは最初の45分、希望想定通りだ。三瀬谷から上流側に11km。標高はほとんど上がっていないのに、雲が厚くなり始めていた。でも今すぐ何かが落ちてくるような気はしない。問題無いだろう。






天ヶ瀬からは立ち上がる山の斜面が急になり、渓谷全体が急に山深くなった。道幅は相変わらず狭くなったり広くなったりで、途切れがちの集落の中の方がむしろ狭い箇所が多い。






道路標識はいつの間にか、逆立ちおむすびの国道マークに変わっていた。地図を見ると、さっき天ヶ瀬で国道422が山中から合流していたのだ。そう言えば、なんかそんな分岐信号があったような気がする。道がぐっと田舎っぽく静かになったので、そちらに気を取られていた。




|

|
|

|
||
その国道422は、渓谷がいよいよ狭く山深い雰囲気を帯び始めた古ヶ野で、どこかの山中へ分岐していった。後で調べるとこの道も420番台細道国道ファミリーのメンバーのようだった。こちらの道は名前が県道53に変わり、宮川ダムまでの登り区間へ突入。









ぐっと道幅が狭くなって木々が路上に梢を伸ばし、森の中の道となる。確か宮川ダム外周は標高300m。とりあえず登りは80mだったはず。




|

|
|

|
||
11:50、宮川ダム着。想定ペースには乗れたままだ。このまま行程を順調に進めていきたい。

|
|
|

|
||

2005年の撤退から13年後、初めて眺める宮川貯水池である。湖面の幅自体はそう広くなく、入り組んで奥へ続いてゆくタイプの人造湖だ。切り立った岸辺の山は、もりもりと広葉樹林に厚く覆われて鬱蒼としている。入り組んだ湖岸の山側はがけが露出し、木々が道に覆い被さっている。ダムから先更に細くなった道道53の路上には、岩の細片が絶えない。人間の領域が森に勝負を掛けるハードボイルドな雰囲気は、ここまでの人里でみられた細道の整然とした親しげな表情とは全く別だ。まさに紀伊半島の、コアな細道のイメージ通りだ。




|

|
|

|
||




|

|
|

|
||

|

|
|

|
||
しかしそういうワイルドな雰囲気の道なのに、意外にもかなり古びた公衆便所(夜は足を踏み入れたくない位)や水場など、そういう裁けたものがしばしば現れるのが特徴的だ。おそらく道の開通時に作られた物と思われる。特に、こんな谷の奥まで来て、食堂が存在するのには驚いた。





12:10、新大杉橋着。かなり細い鉄骨橋で県道53は対岸へ分岐し、道の標識は県道603に変わった。いよいよ水呑峠を越える道の名前である。



橋からまだしばらく湖岸沿いだと思っていたら、意外にすぐ湖岸を離れ、桑木谷をぐいぐい登り始めた。このまま峠の短いトンネルまで続く登りである。

|

|
|

|
||
地形図では、一見谷の折り返し地点まで等高線があまり横断していないように読めた。このためしばらくあまり登らないと思っていた。実際には早くも面白いように高度が上がっている。地形図をよく見直すと、確かに湖面から折り返しまで70m以上登っているはずなのだった。



道は山腹を登り続けた。ルートラボの通り斜度はほぼ均等で、10%程度。これならギヤをぐっと下げ、淡々と登ってゆける。まあ遅いが。



周囲の森は、広葉樹林と杉林が入れ替わって続いた。杉も植林だと思われるが、奥武蔵のような整った雰囲気は全く見られない。どちらにしても鬱蒼と深い森である。森の中には猿が多い。



時には行く手の道を横切って山中へ逃げていったり、斜面の上の方からギャーギャーと、多分こちらに向かって鳴いていた。恐らく威嚇しているのだ。路上には真新しい緑色の糞もみられる。熊の看板が無いのが救いである。熊も猿には辟易するだろう。






谷間の道から、行く手正面の切り立った斜面に道がくちゃくちゃ貼り付いているのが下からよく見えた。峠手前のつづら折れだろう。たかだか100~200mの標高差に思えないほど上に道が見え、心が折れそうになるものの、視覚はあまり当てにならないことも毎度の事だ。あと200mと知っていれば、いつもの200mである。


つづら折れの上からは、深い谷間と緑もこもこながら鋭角的に切り立つ山々、そしてさっき通ってきたばかりの道が見下ろせた。上から眺めると尚更、山間にくねくねと随分細い道である。




|

|
|

|
||
峠近くの稜線には丸裸の斜面も見えた。森を伐採してその後なかなか木が定着しにくいのか、それとも何年か前に大伐採したばかりなのか。

|

|
|

|
||
ひょろひょろと草だか樹だかよくわからない茂みの斜面は、何とも他でみかけない異様な雰囲気を醸し、13年前の崩落によりなかなか開通してくれなかったこの道に箔を付けていた。

|

|
|

|
||

|
||
R0010202.JPG 2018/4/27 紀伊半島Tour18#1 三瀬谷→上池原 水呑峠宮川ダム側手前 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA
谷間を見下ろす展望ポイントから最後にひと登り、13:15、水呑峠着。標高650m。

|
R0010203.JPG 2018/4/27 紀伊半島Tour18#1 三瀬谷→上池原 水呑峠水呑トンネル宮川ダム側入口 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA |
|

|
||

|
13年間の思いが叶った瞬間だった。雲は宮川貯水池辺りより更に厚く、やや薄暗い程。しかしこちらは53歳の誕生日。最高のお誕生日プレゼントだ。思えば曇りで風景がやや重い反面、暑くないので水をあまり飲んでいない。雨さえ降ってなければ上々だ。ツーリングの神様、どうもありがとう。
そして、上池原着18時のスケジュールとして、水呑峠から下った海岸の相賀を14時に通過できれば、後は安心できると思っていた。今水呑峠で13時15分なら、かなり上々である。
峠の向こう側には地図通りに怪しげな細道が分岐している。少し東側へ道が続くというような話をネットで読んだ気もするものの、今回はそんな行動は割愛、行程貯金を殖やしておくことにする。

|
R0010204.JPG 2018/4/27 紀伊半島Tour18#1 三瀬谷→上池原 水呑峠水呑トンネル上里側入口 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA |
|

|
||
峠から国道42まではほぼ650mの下りである。20分ぐらいだろうと思っていたら、甘かった。くねくね入り組んだ山肌の細道は、急カーブ連続で意外に距離があり、路面には細かく鋭い岩が散らばっている。それに、ガードレールの外側はほぼ空中だ。怖くて速度を抑えて下ってゆくと、更に時間が掛かる。

|

|
|

|
||

|

|
|

|
||
怖いのと、切り立った道の外側の眺めは大変素晴らしい。見下ろす山々はダイナミックに、そして鋭く隆起し、岩肌は新緑の密林に埋められるように覆われていた。空間が地形と生命で充たされている、そんな感覚につい目を奪われる。遠くには、これから向かう相賀っぽい営みまで見渡すことができた。

|

|
|

|
||
しかしそれと同時に、自分がいる高度も思い出してしまう。全体的には素晴らしい景色もさることながら、むしろ早く下ってしまいたい恐怖の方が強い。

|

|
|

|
||
下りながら、以前水呑峠の代わりに越えた藤阪峠を思い出した。あちらもやはり早く下ってしまいたい細道だった。ただ、藤阪峠は標高520m弱。高所恐怖はこちらの方が大きいと思う。

|

|
|

|
||
標高差700mのボリュームを覚悟しつつ、怖いのであまりあちこち横見しないようにして下る。途中から下り斜度が更に増した。もう気持ちの余裕が無い。あっという間に標高が下がるのが救いだった。

|

|
|

|
||



谷底に降りて折り返し、やっと標高160m。そこから大河内川の谷間がまた長かった。密森に細道がくねくねで、なかなか地図上での位置が進まない。とはいえ、森の中の細道は涼しく静かでとても楽しい。






谷間が拡がって畑や民家が現れ、やっと里っぽくなったところで正面に大型車が通る道が見えた。国道42だった。13:50、上里着。
















想定ペースに乗っているものの、下りの見込みはやや甘く、相賀通過14時は越えそうだ。GPSトラックには、矢口浦・引本と相賀まで海岸を経由するコースが、上方修正オプションのつもりで入っている。2006年に訪れた、内海と漁村の風景が素晴らしかった道だ。しかし今日はこのオプションは割愛し、先へ脚を進めることにする。


この辺の国道42は、熊野市で見かける渋滞の印象ほど車は多くなく、しばし車が途切れることもある程度の交通量だ。しかし、ここまで辿ってきた県道603の静かで危険な細道とは、やはり路上空間が根本的に違う。上里や中里で旧道へ逃避したり、やっと登場した自販機に立ち寄ったりし、何とか脚を進める。
相賀のファミマで小休止。そろそろ腹が減ってきているし、県道760の分岐も近づいている。県道760から先、もう宿まで55km自販機は無い。そして、宿に電話しておく。転落事故が多い国道425を通るなら、国道425に入る前に電話するように言われているのだ。


14:20、相賀発。希望想定14時からは少し遅れてしまったものの、タイミリミット15時からはまだまだ余裕がある。焦らず急ぎすぎず心穏やかに楽しく、粛々と脚を進めよう。
県道760は、相賀から国道425のクチスボダムまでをショートカットする道であり、3月から続いていた工事通行止めが今日の午前中に解除されているはずだ。今日の終着下北山村上北原へ向かう国道425は、尾鷲が支店となっている。県道760が通れなければ、私は相賀から国道42で一旦尾鷲に出て、国道425を起点から登り始めなければならない。やや遠回りのみならず、尾鷲トンネルまで100m強、展望に乏しく交通量の多い道を我慢して登る必要がある。また、この100mは、海岸沿いの尾鷲まで下ることでほぼ丸ごと無駄になってしまう。そして尾鷲からの国道425それ自体は2009年に一度訪れていて、あまり再訪したいとは思っていない。
県道760経由だと、静かな未済経路を通りつつ、尾鷲経由のデメリットが全て解消される。そういう道が、私が訪れる今日の午前中に通行止め解除となって、待ってくれているのだ。やはりこれもツーリングの神様のお誕生プレゼントとしか思えない。

|

|
相賀の分岐から銚子川の谷間に曲がった途端、いきなり交通量が皆無になる。国道42とは全く別の世界なのが何だか可笑しく楽しい。銚子川の対岸、尾鷲トンネルへ向けて山肌を登ってゆく国道42を眺めることもでき、尚更こちらの長閑さが際立つ。
「種蒔き権兵衛の里」などという看板も見られた。「♪ごんべが種蒔きゃ、カラスがほじくる」の歌の起源らしい。そういやあ前回国道42のこの辺を通った2005年にも眺めているな、あれはまさに水呑峠を撤退した時だったっけ、などと思い出す。







|

|
|

|
||
谷間は地形図どおりすぐに狭くなり、谷間の奥、木津の橋で終了。銚子川から支流の又口川となった渓谷の登りが始まった。

|

|
|

|
||
登り斜度は10%ぐらい。今日はもう水呑峠でそれぐらいの登りに対しては免疫があるような気になっている。

|

|
|

|
||
斜度よりも目を引かれたのが、屈曲する狭い渓谷が溢れそうな程ごろごろ転がる巨大な岩だ。どういうわけか巨大な岩はどれも不自然なほど角や面が滑らかで、中には平滑とも言えるような大きな面を持つものもみられた。

|

|
|

|
||
狭い渓谷の川の透明度は凄く、カワトンボが飛び交うのが楽しい。

|

|
|

|
||

|

|
|

|
||
1箇所、いかにも崩落土砂を撤去したばかりのような急斜面があり、これが問題の箇所かと思った。今日開通したばかりということを知っていると、何か谷間全体に対して厳しい雰囲気を感じてしまう。



県道760区間の終盤では、境界線を引いたように突如谷間と川原が拡がり、巨大だった岩も皆無となってごく普通の石の川原に変わった。行く手の小山には、下ってきた国道425が見え始めた。前回2009年八幡トンネル側から下って来たときは、クチスボダムの尾鷲側に軽く登り返しがあったな、などと思い出した。



国道425との合流点には、通行止めのA型バリケードが置かれていた。脇が通行し放題のAバリだし、歩行なら工事の都合をみて注意して通行して欲しい旨を、事前確認済みである。



15:00、クチスボダム着。行程は再び希望想定ペースに乗っていた。県道760のショートカットのお陰だ。標高146m、八幡トンネルは標高540m。あと400m登ればいい。



小さな貯水池はすぐ川原に変わり、そのまま又口川は更に谷間を淡々と遡り続けた。

|

|
|

|
||
切り立った狭い谷間にしては、平たい川原が延々と続くのは前回の記憶通り。というより、9年振りの記憶を現地に来て思い出すことが多い。



今日は尾鷲から山を越えて又口川に合流する国道425じゃなくて、又口川の谷間を県道760で遡ってきたので、山中に不自然な平たい川原が又口川の谷間独特の表情だということがよくわかる。



谷間が狭くなって周囲はやや密な森の中に替わり、国道425は次第に斜度を上げ始めた。森からはあまり景色が開けることは無い。



又口に9年前に見かけた民家は、記憶より大分寂れた佇まいだった。何だか一方的な片思いが肩すかしされたような気分の行き場は無い。



更に山腹の森をとぼとぼてれてれ、あきれるほど登りが遅い。でも出発から80km以上、残りの登り量も距離も次第に少なくなっている。もう焦る気は全くしない。






静かな新緑の森の、楽しい登りである。



時々、上から工事資材を満載した車が下ってきた。通行止め区間の工事車両が、連休に工事現場を閉め、資材共々一旦引き上げるのだろう。ならば工事場所で工事車両は動いていない可能性が高い。自転車なら全く問題無く通行できるかもしれない。




|

|
|

|
||
峠の少し手前で、周囲の展望が開け始めた。前回眺めた風景、というより写真で何度も眺めている山々を眺めてみる。写真では夕方の赤い光に染まっていた山々は、今日は雲の下でやや重い色だ。しかし天気予報通り雨が降る気配は無いし、これで今日のまとまった登りはほとんど終了なのだ。このまま脚を進め、一気にトンネルを抜け、下ってしまえ。

R0010205.JPG 2018/4/27 紀伊半島Tour18#1 三瀬谷→上池原 八幡トンネル手前 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA |

|
|

|
||
16:15、八幡トンネル着。ここまで通行止めの原因らしい箇所は全く無かったが、トンネル入口にやっとその工事現場があった。その実態は、トンネル入口のすぐ手前で、大きな岩や土砂が道幅の90%位にうず高く崩落している、というものだった。



これを撤去するまで、車の通行は明らかに無理だということが一目でわかる。オートバイもなかなか厳しい。まさに歩いてなんとか通過できる、という位のものである。自転車の私は、2~30m担いでそっと通過させていただく。
トンネルの尾鷲側が空中に開けた山の斜面だったのとは対照的に、上北山村側は岩が切り立つ渓谷の底である。

|
R0010206.JPG 2018/4/27 紀伊半島Tour18#1 三瀬谷→上池原 八幡トンネルナゴセ側入口 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA |
|

|
||
広葉樹の新緑が瑞々しく生い茂るのはさることながら、道の山側の岩肌や、川原にごろごろ転がる岩がごつごつ荒々しい。






谷間のやや厳しい表情は、国道309の川迫渓谷にちょっとだけ似ているような気がする。あちらは浮世離れした印象が勝ち、こちらは厳しさの印象が強い。2009年の訪問時は余程泡を食っていたのか、こういう渓谷を眺めた記憶があまり無い。或いは川迫渓谷の印象があまりにも強く、訪問の記憶として心に残ったのかもしれない。

|

|
|

|
||
今改めて、やや頼りない人工物が自然に無駄な抵抗をしているような、何というかハードボイルドでスパルタンな道の表情が、国道425独特のものなのかもしれないと気付き始めていた。



坂本貯水池に下ってしまう前に、地形図にナゴセと片仮名で名前が書かれている集落がある。



集落というより、今となっては空き家が集まっている場所という方が正しい。2009年に少しは生活感のようなものを見つけることができたような気がする。



ナゴセから先、下り斜度が落ちついて川面が谷間一杯に拡がった。坂本貯水池が始まったのだった。

|

|
|

|
||
坂本貯水池湖岸でも道幅は相変わらず細く、上流川からダムまでほぼ平坦だ。道は上流部の対岸が近い場所では切り立って入り組む岩場に貼り付き、湖面も行く手もよく見渡せる。

|

|
|

|
||
湖の幅が拡がり始めると道は木立の中に続く。木が茂っているため、湖面はちらちら見える程度になる。

|

|
|

|
||

|
||
時々釣り人のものらしき車が道端に停まっていた。車に人気は無いものの、クチスボダムからここまで一般車がほぼ皆無だったため、何だか懐かしいような嬉しい気分になる。

|

|
|

|
||

|

|
|

|
||



不動橋、出会橋と、ここが国道425だとわかっていてもか細く感じる橋で湖面を渡った後、坂本ダムまで意外にすぐ到着。前回2009年訪問時の、池原貯水池+坂本貯水池区間の長い長いという印象があったため、意外に短く感じているのかもしれない。

|

|
|

|
||
坂本ダムと池原貯水池は完全に連続していてて、国道425の湖岸区間は合計20kmにもなる。池原貯水池の外周道路も坂本貯水池と同じく木立の中だが、木立の茂みが深く、湖の展望が見えそうで見えないぐらいに遮られることが増えた。



坂本ダムから下流の池原ダムへ少し下った後、早くも道が登り返し始めた。池原ダムの外周区間にはけっこうアップダウンがあることをやっと思い出した。






アップダウンは最大40mぐらい。岬越えのよくあるパターンのものが多く、次から次へ途切れることが無い。池原貯水池湖岸だけで標高差100mは軽くありそうだ。そういえば前回、果てしないアップダウンにうんざりしたんだった。






相変わらず道幅は狭くカーブは厳しい。カーブミラーはあっても、路面が少し荒れていたり岩が散らばっていて、下りでも20km/h台前半ぐらいしか出していない。

|

|
|

|
||




|

|
|

|
||
対岸に切り立つ山が木立の向こうにちらちら見える。所々岩肌が露わで、そうでないところは新緑色とりどりの広葉樹林が密に茂っている。




貯水池全体として果てしなく山深く、これはこれで国道425の際だって個性ある区間だと思う。

|

|
|

|
||

|

|
|

|
||



しかしカーブと等高線と周囲の風景により、少しづつ池原ダムまで次第に近づいていることはわかっていた。

|

|
|

|
||



湖岸区間終盤では、1日楽しんでそろそろ帰り始める観光客のものらしきワゴン車が急に増えた。




|

|
|

|
||
正面に池原ダムの構造体が現われ、最後の坂を下ったことがわかった。



17:40、池原ダム着。ダムサイトから堤体へ続く細道がそのまま国道425指定の道となっていて、一度対岸に進んだ道が更にその先で別の堤体上を渡っているのが見渡せる

|

|
|

|
||
堤体を挟んだ貯水池の反対側は100mの高低差で落ち込んでいて、うねる谷間に北山川がジオラマのように見下ろせる。
R0010207.JPG 2018/4/27 紀伊半島Tour18#1 三瀬谷→上池原 池原ダム1谷間側 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA
2009年に見た風景、いや、空間感覚を思い出した。三瀬谷から120km。オプションコースは省略したものの、急がず焦らず淡々と、しかも楽しみつつ、希望予定通りに池原ダムまで着くことができたのを実感できた。

二つ目のダム堤体を渡る手前で、細道が分岐して道端の森へ下ってゆくのに気が付いた。というよりこの道、地形図では破線で描かれている。この後宿に着くには、ダム堤体から対岸に渡って国道169に合流し、谷底へ100m以上一気に下り、再び対岸から北山川をこちら岸に渡ることになる。その行程を、手前の山の中だけでショートカットする道なのだ。
道の存在は当然のように意識していた。破線だったのでダートか山道なのではないかと思っていた道が、今もの前では普通の白抜き細道ぐらいの舗装道路であり、ひょっとしてこのまま下まで舗装なのではないかとも思われる。



とりあえず、と思って行ってみると、結局下まで全く問題のない舗装道路が続いた。最後の嬉しいショートカットだった。



北山ダムの下、ぐるっと回り込む谷底に、運動場や温浴・宿泊施設を備えた「下北山きなりの郷」がある。裏手から敷地に降りて宿泊施設棟を探していると、「下北山きなりの郷」という看板を発見。この施設自体、2002年の初紀伊半島で見かけていることをようやく思い出した。何事も再訪しないと思い出せない。
荷物を降ろして宿の手続きを終えて18:00。最後はぴったり、こうだといいなという目論見通りだった。何か無理をした訳じゃない。写真だって撮る場所で撮っている。9年振りの国道425も心に残る良い道だったし、コース全体を比較的かっちり決めてきた今回の5日間に自信が持てるようになった、幸先のいい1日だった。




|

|
団体のお客さんが別室で宴会中のため、夕食は通常の食堂で私一人。オプション無しの通常メニューだったが、充分に充実していてとても美味しい。HPで見かけた温浴施設併設レストランのピザの写真がとても美味しそうで、夕食後に絶対食べに行こうと思っていたが、全く必要無くお腹いっぱい大満足なのだった。
記 2018/5/20