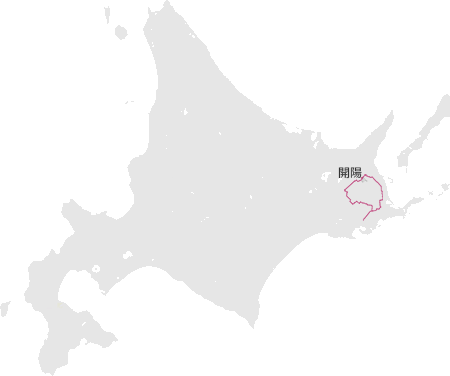
開陽→俵橋
(以上#2-1)
(以下#2-2)
→別海温泉
(以上#2-2)
(以下#2-3)
→上風連
(以上#2-3)
(以下#2-4)
→奥別寒辺牛
(以上#2-4)
(以下#2-5)
→上風連
(以上#2-5)
(以下#2-6)
→西春別
(以上#2-6)
(以下#2-7)
→萩野
(以上#2-7)
(以下#2-8)
→開陽台
(以上#2-8)
203km
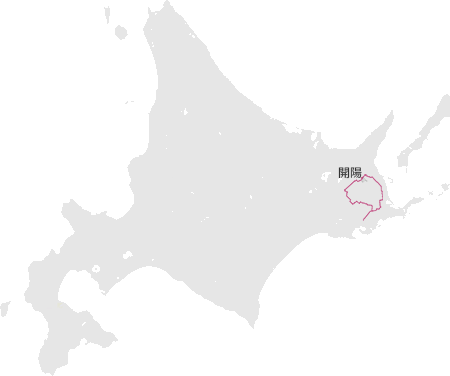
|
|
|
朝の4時、夜明けの早い北海道でも、窓の外はまだ真っ暗だ。でも、東京で4時に起きても身体を動かす気が全く起こらないのに、場所が北海道でツーリング中だからか、動かなきゃと思えて身体も動くのが我ながら大変可笑しい。そう言えば10日ぐらい前、7月末に尾瀬で4時半から燧ヶ岳登山したときも身体も気持ちもちゃんと行動体制になってくれた。東京での暑さ疲れも取れているようだし、粛々とこの後も行動を進めよう。等と考えるのももどかしく、クロワッサンや甘めのデニッシュ、おにぎりもボトルの水で腹に流し込んでゆく。
4時15分頃には外が明るくなり始めた。薄暗いうちから、どうやら天気予報通り晴れているらしいことがわかった。根釧台地202kmコース出発に向け、最大の懸案がクリアになった。

 ■
■

|
荷物をまとめて一段落すると5時前。いい時間だ。外へ出ると辺りに朝陽が差し、小粒の雲の隙間に青空が見えている。昨日は曇りだったが、もともと到着時刻が遅く行動の潰しが利かない日だった。そして夜のうちに軽く雨が降り、夜明けに雨が上がって晴れた。今日の行動には都合のいい展開である。今日以外にも、今年は初詣で訪れた気象神社の、桐箱入りお守りの御利益に預かることが多いように思う。
5:20、民宿地平線発。まずは町道北19で武佐へ。
■

 ■
■


頭上は青空だが朝陽は雲に隠れているのに、意外にも湿度が高く気温は余り低くなく、むっとした感覚がある。ひんやりした涼しさは全く無い。中標津の早朝でこれだと、この後フリースなんて使う機会は無いだろうな。



武佐への下りでGR3の電池の調子が悪く時々脚を停めたものの、走り出すと身体は快調で不安は無さそうだ。とはいえ、まだ4サイドの自転車感覚に身体が慣れていないように感じられる。それに路面は所々濡れているので、滑らないように気をつけねば。何しろ歳だ。



武佐にはこのコースで珍しい自販機はあり、雨が降っても立ち寄っておく場合もあるものの、今年は通過しておく。



道道774をクランクで通過して農道へ。行く手の空が曇り始めている。しかし雲は低くない。雨さえ降らなければ、むしろ暑くなくてこの後好都合かもしれない。そのぐらい朝から気温が高い。



牧草地の丘を、直交する農道や町道を移ってゆき、俵橋から南下しつつ次第に海岸寄りの標津の低地へと向かってゆく。



以前使っていた、1986年に買った地形図には、この辺りから別海町にかけて道がほとんど載っていない。私がこの辺りを道道11と国道244以外の道でコース取りして走るようになったのは、予めWeb地図(当時はルートラボ)で描いたコースをGPSに入れておき、それをなぞって走るようになった2007~8年頃からじゃなかったかと思う。その点根釧台地202kmコース(と根釧台地100kmコース)は、道道11からオホーツク沿岸寄りの眺めのいい道を適切に渡り歩き、別海まで延々南下する道道994に繋いでゆくという点が、大変上手いコース取りだと思う。そしてこの辺は、適度に変化しつつ根釧台地の距離感を存分に味わえる、202kmコース序盤の見所にもなっているのだ。


 2
2昨日夕陽を眺めた丘を経由しつつ、時々向きを変えたり直交して道を1区画平行移動していたりした道は、標津川を渡る辺りからひたすら直線基調になり、丘の牧草地から低地の谷間を越えてゆくようになった。低地は大体熊が出てきそうな川原の茂みであり、段丘部分の防風林みたいな森も何だか不気味である。

 ■
■
牧草地と防風林、写真で見覚えのある風景が、エリア毎の雰囲気とともに過ぎてゆく。



台地上の牧草地に牧場が現れ始めると、交差点の看板の地名が標津から中標津に替わる。その後は中春別となるはずなのだが、それまでが長いはずだ。そして、それが別海に替わらないとこの区間は延々と続く筈であり、中春別から別海に替わってからが一番長いはずなのだ。



看板の地名にやっと中春別が現れ、コースが道に突き当たってクランクしてから、別海の地名が現れるまでしばらく掛かったのは記憶通り。












そして看板の地名が別海に替わると、時々現れる道路標識の内陸側は別海だけであり、海岸方面は尾岱沼、床丹と次第に替わってゆく。



 ■
■




202kmコースはこの後別海町から浜中町、折り返し地点手前で厚岸町に脚を踏み入れるものの、折り返してコース西端手前まで別海町に続いている。つまり別海町は202kmコースの中核を占めると言ってよく、それは根釧台地の中核でもあることを気付かされる。




 ■
■
道がややイレギュラーに曲がり始めると、コースの大きな流れとしては西へ向かい始める、はずだった。しかしそこからも南下が続き、記憶にある風景もやはり南下区間の風景が続いた。




何しろ長い長い、標津・中春別・別海区間なのだった。


 ■
■




 ■
■


細目の町道や路面が鄙びた感じの農道、明らかに一続きではない道を突き当たりなどで分節的に渡り歩きはじめても、道が西へ向き始めるまでにまだしばらくかかった。








 ■
■
分節的な道がいつの間にかトータルで西向きに変わり、牧草地から防風林をいくつか渡り行く手に塔が見え、唐突に、しかしやっと道道11に合流。位置的には別海市街の少し南、元別海温泉の少し北。








道道11のクランク経由は2~300m。根釧台地の周回コースとして、この202kmコースが根釧台地の主要幹線道路を少しだけ経由しておく、そのことに意義がある。

 3
3次は新酪農道へ。



道と防風林がどこまでも延々とひたすら平行し直行している中標津と違い、別海町の道は角度がややイレギュラー気味に彫りの深い地形を辿ってゆく。必ずしも谷間や川に沿っているというわけではなく、台地上で方向を変えたり、時には一直線道路がいくつも谷間を越えたり、無駄にイレギュラーなように見える場合がある。








新酪農道に入り、道道11の近くでは地形が比較的安定していたのが、新酪展望台の手前から盛大なアップダウンが現れ始めた。






一直線に続いてゆく道が谷を越え、次の丘を直登で登ってゆく。開陽からここまでの根釧台地で見ることが無かった光景だ。道の彼方にやや大きな丘越えと谷が続いているのを眺めると、ややうんざりする。ただ実際に先に進んでみると、直登を手前の坂の上から眺めるほど実際の登り量がある訳ではないこともわかる。



道を走りながら景色を眺めていると、波打つような地形が動いているように劇的に変わってゆく。道道11はこういう地形の境となっているのだ。他にも道道11を越えると天気ががらっと変わったり、時には避難中のバス車内で道道11で天気が分かれるのを眺めたこともある。根釧台地のエリアを分ける、道道11の幹線道路たる所以と言える。



前半区間もいよいよ次の段階に入ったこの段階で、今日はまだ風があまり吹いていない。今のところ風に悩まされていないのは有り難いことだ。ただ、天気が急に変わるのは根釧台地で珍しいことじゃないので、このあといきなり風が吹き荒れ始めても全然驚きは無い。悪態はつくと思う。


3度目の登りで台地に乗り上げ、何度か道を乗り換えた後道は西へ向きを変えた。こうなると上風連が近くなってきているはずだ。しかし、いつの間にか低くなっていた雲が降りてきて、辺りがふわっと霧雨に包まれ、服に細かい霧粒が付き始めた。まだ雨具を着るほどじゃない。













8:55上風連着。雲が低く、湿度というより細かい水滴の密度が上がり、遠景が霞み始めている。まあ、あまり大したことにはならないとは思う。
前回2年前と同じく、9時開店のはずのA-COOPに全く人気は無い。閉店したとは聞いていないので、今回もまだ営業時間外なので開いてないんだろうな。こちらは202kmコースで数少ないお店のうちのひとつ、森重商店に表敬訪問し自販機でコーヒーでも飲むことにする。森重商店とA-COOPの他、上風連には公民館もあり、その気になれば水が飲めたかなあ、とか確か自販機もあったかなあ、等と思いながら道道449の交差点へ向かって脚を進めてゆく。
交差点の手前から、それまで霧雨だったのがはっきりした天気の境界の向こうで水滴の密度が上がり、弱い雨に変わった。雨粒が細かいのであまり濡れた感じがしないのに、服がしっとりする要注意のパターンの雨だ。こういう時に雨具を着込んでおかないといけないことはわかっている。立ち止まる気にならないことがこういう雨の怖いところだとわかっている。それでもやはりそのまま脚を進めてしまうのは、けっこう暑くて化繊Tシャツが汗で濡れているからかもしれない。などと他人事の様に思う。戻るわけにはいかないというより、今はこのコースで先へ進みたい気分である、ということが何となく嬉しい。


道道813の分岐には「大別方面」の看板が立っている。「別寒辺牛湿原とかその先の大別もしばらく行ってないな」などと思いつつ、道道813へ脚を進めてゆく。



雨はまだ降っている。服は濡れているという程ではないものの、そろそろ自転車の金属部分に付いた水滴が形になり始めている。それでもまだ雨具を着ていないのは、何とかまだ濡れきっていないのと、それ以上にけっこう暑いからだ。これで日が照ったらかなり暑いだろう。ある意味この天気で助かっているのであった。






開進の防風林が印象的な丘から、西円の一直線区間が始まった。





すぐアップダウンがありまず浜中町界を通過。谷の牧草地から丘を一つ越えると排水処理場(と言っても一見では茂みに放置気味の小さな建物が建っているだけ)、丘を越えた次の谷間でJA浜中町西円取扱所通過。この取扱所があるのは一直線区間の意外に東の方なのだということを、訪問の度に次第に私は理解できている。



この段階で9:30。上風連で自販機に立ち寄ったばかりではあるものの、この根釧台地まっただ中に立つ西部劇で出てくる荒野の水場のようなJA取扱所に表敬訪問しておく。ここにこんな補給地点があることには、毎回大変感謝している。もちろんJA浜中町としても、酪農地帯のど真ん中の「取扱所」、多分酪農関係の重要拠点なのだろう。
閉まっている店の前で脚を停め、自販機コーヒー休憩とする。雨は再び霧雨ぐらいに弱まり始めていた。というより、リスク管理上は緊急に雨具の必要が無い、ということを警戒すべきかもしれない。とは思いつつ、やはり雨具はまだ着ない。それほど暑いのである。



トライベツへの農道、道道807の交差点を過ぎ、谷間と丘を突っ切って一直線の道は続く。正面から眺める丘への直登登りは、眺めていてげんなりするものの、行ってみるとそれほど厳しい登りではない。遠景の圧縮効果で壁の様に見えるだけなのだ。まあ、北海道でそんな風景を眺める度にげんなりしていたら商売上がったりではある。



そんなアップダウンが2~3回、まだまだだと思っていると意外に早く遙か前方が道じゃなくて森で塞がっているのが見え始めるのであった。あの辺まで行けば道が曲がり、谷間を横断して高知へ入るのである。しかしそれからなかなか見える辺りが近づいてこないのも記憶通りで「まあ、そんなもんだよ」などと思う。



西円の先で道は乾き始め、雨はすっかり上がった。服が濡れきる手前だった。危ない危ない。雨具を着る気にならなかったほど暑かっただけあり、雨のせいじゃなく汗で化繊Tシャツはだぼだぼになっている。当面乾きにくいかもしれない。



低地の谷に降り、道は谷に沿って僅かに向きを変えてゆく。浜中・厚岸町境を越え、厚岸の台地上のグリッドへと角度を修正してゆくのだ。浜中・厚岸とそれぞれ両側からに牧場開発がきっちりした区画で内側に進んでゆき、最後に谷間で道をつなげたんじゃないのか。そんな想像が楽しい、折り返し地点までの最後の区間だ。



そういう想像をしつつ厚岸町まで脚を踏み入れるように組まれているのも、このコースの含蓄のひとつであり、大きな見せ場だと改めて思う。根釧台地南部随一の一直線道路である道道813を通り、かつ忘れちゃあいかんぞ、と言わんばかりに厚岸町にも程良く脚を踏み入れるようコースが組まれつつ、更にそういう見所が隠されているのだ。






道が台地上に登り、高知小学校跡(一見水が飲めそうで飲めない悔しさとともに印象深い)、知床半島の山々まで一望できるはずの牧草地を過ぎ、10:15、奥別寒辺牛の折り返し地点に到着。ここで94km。
過去最高ペースだった前回より5分遅いだけの、なかなか順調な行程のようではある。しかしかなり強い向かい風が無いのに5分遅れ、ということはそんなに快調じゃないのかとも思う。それに、前回向かい風の分追い風アシストとなった復路のペースは、今回は望めないだろう。でもまあ、ここまで比較的淡々とした展開で来れているので、まずは順調なのかもしれないとは思える。
ここから始まる別寒辺牛湿原の森(というより樹海)に下ってゆく道道813を眺めつつ、パンを食べておく。9時前に上風連でちょっと食べてから、1時間半近く経ってそろそろ腹が減り始めている。ツーリング中のいい感覚である。無事北海道ツーリングに戻って来れた、という実感がとても嬉しい。今日は、いや、今後もこの感じを忘れず、意識して適切な補給間隔を心がけたい。
10:25、奥別寒辺牛発。



高知の牧草地、牧場、小学校跡と来た道を戻ってゆく。



やはり、前回20分で西円取扱所に着いてしまったような追い風は、今年は無い。ただ、前回の往路のような身体を削り取られそうな向い風も無かった。有り難いことに、往路より雲が高くなり始めている。相変わらずそこそこ以上に暑いので、このまま晴れずにそこそこ明るい風景を眺められるぐらいの天気が続くといいな。



淡々と厚岸町界の谷から一直線区間へ。アップダウン、トライベツ・東円分岐とさっき来た道を戻ってゆく。同じ場所の一本道で、行きと帰りで風景に飽きないのが有り難い。



道はもう完全に乾いている。もう雨の心配は無いだろう。



11:10西円取扱所着。帰りなので、自販機に立ち寄っておく。またいつか。
再び出発すると、自販機に少し立ち寄っている間に辺りが明るくなっているのがわかった。雲も少しずつ高くなっているようだ。が、やはりそこそこ厚く低くもあり、あまりすかっと晴れそうにもない。相変わらず風は吹きそうにも無いのが救いではある。






一直線区間から台地へ登り、11:15、開新の道道928分岐着。




開陽からここまで110km、出発から6時間。名実ともにコース全体の半分以上を走ったことになる。コース全体として、奥別寒辺牛折り返し区間から北上区間へ移行するとともに、ここからコースが本格的に復路となる。


道道928は、台地からやや彫りの深い豪快な谷をいくつも越え、豪快に北へ突き進む。地名は開新から再び上風連となっていて、西側に自衛隊矢臼別演習場の森が続いている。



彫りの深い谷は別海町南部、特に上風連辺りの地形の特徴であり、根釧台地も核心地域にやって来たという気分にさせられる。往路に上風連へ向かった道でも、新酪農道に入った途端にこういう大きな谷間を通っている。



 6
6西側に続いていた森が牧草地に変わり、谷を2~3回越えて周囲の雰囲気が広々と拡がり始めた。交差点からコースは北西へ向かい始めた。自衛隊矢臼別駐屯地の北側区間に入ったのだ。根釧台地の南西にどかっと居座るように位置する自衛隊矢臼別駐屯地と別寒辺牛湿原の大森林の北側から標茶東側、根釧台地北東縁の道道13に突き当たるまで北西向きが続く。ここも202kmコースの大きな一片を担う、大変長い区間だ。







台地上に乗り上げ、比較的安定した地形に続いてゆく道の左は自衛隊矢臼別演習場、右は防風林か牧草地が続く。自衛隊矢臼別演習場への入口でクランク状に北へ1本ずれ、更に別海町畜牛育成牧場沿いに続いてゆく。道が森沿いから牧草地の中へ移ると、軽い横風が吹き始めているのが感じられた。







12:25、130km辺りの牧草地で少し脚を停める。南側は矢臼別演習場、というより別寒辺牛湿原の奥に続く森。北側は軽く波打つような地形の牧草地が拡がり、晴れていれば西別岳・武佐岳から知床の山々が一望できるはずの場所だ。今日はその遠景が雲に隠れて全く見えない。そして曇っていても蒸し暑い。汗がだらだら出ている。空の雲は比較的明るく低くはないもののやや厚そうで、けっこうしつこそうだ。晴れる感じは無い。













 ■
■
道が演習場の森から離れ、西春別に近づき始める別海町畜牛育成牧場の辺りでは、道沿いのカラマツの森が丸ごと伐採されて数年経つ箇所がある。再び小さな木が生長し始めているその場所で、いつかこの道で、この木が大きくなって森になるのを見届けることができるだろうかなどと思う。20年後ぐらいか…見れないだろうな。

 ■
■




 ■
■



西春別の外れでは、西北向きのコースが少し北にスライドする。国道272を渡ったすぐ向こうに、確か自販機があった。それは工事関係の現場事務所だったような気がする。あると思って通ったときにはそれが無くなっていたようにもに思うので、話がややこしい。都合の良いことと悪いことは、都合の良い方を憶える傾向が私にはあるので、こういうことになるのだ。
しかし、そのもう少し手前で行く手の道沿いに赤い点が現れた。思わず「何でしょうあれわぁああ!」などと口走りつつ、そういえば自販機が設けられている牧場を前回見つけたことを思い出した。次第にその赤い点に近づき、今回もその牧場「きぼうファーム」に自販機は変わること無く立っていてくれたことがわかった。「きぼうファーム」は、自販機が無かったとしてもお願いすれば水をいただけそうな、人っ気のある牧場ではある。でもやはり、自販機の極端に少ないこの202kmコースで、特に商店自販機空白地帯のど真ん中だったこの場所に、自販機が建っているのは大変有り難い。
そして国道272を横断した向こう側には、やはり自販機は既に無かった。と書いておかないと、次回以降またそれを忘れて期待してしまう。









 7
7国道272の先で、202kmコースから少し外れて西へ向かう。前回はほぼ全区間純正コースだったので、今年は少し大回りにしてみたのだ。
■





トラックを描くときに選んだ道は、舗装路のつもりだったのに実際にはダートだったので、その先の舗装道へ。純正コースからあまり離れていないのに、牧場と牧場の間の生活道のような、静かで穏やかなした雰囲気の道が続いた。それは別海南部から浜中町辺り、かなり人口密度が少ないとにかくだだっ広い牧草地ではなく、西春別・計根別辺りの台地上に拡がっている、もう少し牧場っぽい雰囲気だ。地形にあまり大規模なアップダウンが無いのも一役買っている。





純正コースより少し南を通っているはずではあるものの、見たことが無い風景が続き、次第に方向感覚と位置が全然わからなくなってきた。ただ、時々確認するGPSトラックからは外れていないので、間違っていないはず。それに時々南側の防風林の向こうに車の音が聞こえるような気もする。国道272の車の音かもしれない。自分で経路を描いているのに現在位置の感覚があまり無いのは、やはり想像込みでコースを描いているんだろうな。などと思いながら牧草地と防風林、そして現れ始めた軽いアップダウンを進んでゆく。アップダウンがあるということは、中春別から泉川に移りつつあるのかもしれない。


 ■
■


防風林の向こうに現れたT字路から北に向かった道は、明らかに通ったことがある。国道272から北西へ向かう道である。ここでやっと位置もわかった。確かに泉川だが、だだっ広い泉川のかなり南である。もう少し位置が進んでいると思っていた。まだここなのか。と思っているということは、この辺の距離感覚が自分には無いのである。そして、自分で描いたトラックの大回り具合もすっかり忘れているのだった。
道については風景を憶えているだけあり、ダイナミックな展開、すなわち地形の起伏そのものに変化がある。ということは即アップダウンである。のみならず、しかもそれが、記憶通りにやや際限無く続いてゆくのであった。泉川の谷間まで、やや調子に乗って大回りコースを描いたんだった。自分ですっかり忘れている。

 ■
■










台地上から豪快に下った川沿いの、牧草地でも防風林でもないちょっと不気味な放置気味の茂みは、間違いなく泉川の、元標津線の泉川駅があった谷間である。やっとここまで来た。そして道道13までまだもう10kmぐらいあったはず。



ここは以前石川さんに車で案内していただいた。泉川でいつも思い出すのは、私が標津線の標茶区間に1回だけ乗った1986年の冬。その時は羅臼で早起きしたのに加え、キハ22の暖房が例によって効き過ぎていて、中標津を出てから確かほとんど居眠りしていた。曇った駅名標とか電柱以外は真っ白なだけの車窓風景が妙に印象に残っている。




しばしイレギュラーに道が屈曲する間牧場とやや鬱蒼とした茂みと森が断続し、台地に乗り上げてから道道13までは数km一直線。少しづつ登る道なのに、一直線の道と拡がる牧草地のせいで登りが意識できない。意外なほど進まないというストレスで疲れを意識し始める。思えばもう出発から8時間以上経っているのだ、等と思ったりもする。

 ■
■
風景自体は、整然と区画された牧草地が程良い地形の変化とともに続く、この辺りならではの楽しさがある。晴れるとしょっちゅう脚が停まるような素敵な眺めであり、根釧台地の外れでもあるためかこの辺から都合良く晴れてくれる年もあるのだが、今年はずっと曇りのようだ。まあ、雨が降らなければ御の字である。
■

 ■
■


道道13に合流するとともに、コースは別海町から標茶町へ。というよりここまで別海町だったことが凄い。別海町はやはり根釧台地の中核部なのだ。
根釧台地縁の稜線部を辿った後、稜線部から再び根釧台地内に降りてスノーシェッド先の最高地点を越え、更に根釧台地を見渡しながらその中へ降りてゆく。広々と見渡す空間に、知床から続く山々の裾から根釧台地が拡がっているのがよく感じられる。この辺ならではの風景であり、コースもいよいよ終盤のパートに入りつつあることを感じさせる。
国道243に下りきる前に、萩野まで農道を経由する区間は、とても静かな道なので毎回この辺の道を通るときに楽しみにしている。道道13でも今日のコースの中では幹線道路であり、車が多い道なのだ。そしてここを通るお陰で、萩野では国道243の経由距離が数10mで済むのだ。







分岐の標高166mから防風林と牧場の間を登り返し、農道の最高地点は標高210m。開陽台周辺を除けばこのコース随一の高所でもある。

 ■
■



道がカーブしている丘の上は防風林に囲まれていて、畑と牧草地が拡がっている。今日のコースでは珍しい、詩的にこぢんまりした空間だ。以前は牧草地だったような気がする道沿いの一角は、今回は重機が土の入れ替えをしていた。




 8
8丘から下って15:05、萩野着。国道243をクランク経由して道道885へ。






いよいよ中標津到着が見えてきた。帰ってきたという安心感とともに、谷間に向かって一直線の道をのんびり下ってゆく。流石にちょっと疲れは感じられるものの、もうあと30kmちょっとのはず。そして根釧台地で一番慣れ親しんだ、ホームグラウンドのような気がする道でもある。通過時刻は一見遅れ始めているようにも思えるが、前回より多少大回りコースだったのを考えるとまあ妥当でもあり、前回とほぼ同じペースと言って良いだろう。向い風、追い風の条件が加わった前回と結果的にあまり変わらないことは、少し不思議ではある。そういうものかもしれない。
■






 ■
■
上虹別から西別岳登山口、町界を越えて中標津町へと続く道沿いには、防風林と防風林に区画された牧草地が整然と続く。基本的な要素は今日ずっと続いていた風景と全く同じなのだが、こちらでは形も大きさも整然とした区画で牧草地と防風林が続き、それが風景のリズムになっている。また、山裾故の地形の変化のためか背景の山や下手側の根釧台地による開放感が特徴的であり、これらの視覚としてわかりやすい構成が他の場所には無い風景の魅力に繋がっているのだ。1日根釧台地を巡ってきた後では、尚更その独特さが理解できるように思う。
■

 ■
■


15:35、ながかわ商店着。
毎度の缶コーヒー休憩とする。このコース、自販機があれば表敬訪問ぐらいしておかねば。天気は相変わらず曇りであり、あまり風景に脚を停めることは無かったものの、やはり去年より多少遅れている。大回りが効いているのかもしれない。ただ、去年は虹別から先で風景の写真を撮るために脚を停め、かなりペースダウンしている。今年はそれが無い。まあ諸々込みで、何と言ってももう到着が見えている。あまり何も考えずに進めば良いだけだ。
養老牛、旭新養老牛、谷間越えでバウンドする以外北進手前まで一直線。武佐岳へ続く山の姿が近づき、山裾が拡がり、下手側は防風林の向こうに時々地平線が拡がる。
■



 ■
■
虹別から開陽を経由し武佐まで続く根釧台地北側山裾の1本道、道道885・150・町道北19の、私的ハイライトである。今日は雲が低く、あまり脚を停めずに風景を眺めつつ淡々と通過してゆく。
■



 ■
■



北進から、一直線だった道が南向きへ曲がり始め、谷間をいくつか軽く越えてゆく。途中で道道150から南へ山裾から1本南へスライドする。202kmの純正コースを逸れて俣落までの根釧台地随一の豪快な下りを割愛することになるものの、こちらは落ちついた雰囲気で推移しつつ、広々とした牧草地と斜め気味に横切ってゆく防風林が眺めの変化を付けてくれる。この北進・俣落の南回り区間は我流202kmコースである。そう言えばもともと、初期の根釧台地202km手描き地図では、道道150から分岐して戻ってくる開陽台隣の牧草地のダート登り下りが202kmコースに含まれていた。この区間はその後の版では202kmコースに含まれないようになっていたのだが、映画「家族」ラストシーンにも出てくる丘でもある。








16:35、俣落着。風景にあまり脚を停めることは無かったのでもう少し早く着くかとも思っていたが、こんなもんかもしれない。



俣落からは町道北19。朝に武佐へ向かった道の、民宿地平線を挟んで反対側の道だ。



開陽台入口まで登った後、開陽台入口から先は躊躇無く全押しで登る。約200km走った後だという言い訳が、今の私にはちゃんとある。



ただ、毎度思うが何故登り側の道で、わざわざ全体の距離の半分ぐらいでほぼ駐車場ぐらいの高さまで登った後、一度下って登り返しているのか。これが開陽台への登りを厳しくしているのに。
■



 ■
■
17:00、開陽台着。
展望台から見えるのは、やはり雲の下の、やや薄暗い根釧台地である。そして天気に拘わらず、また来れたという満足感が全く変わらないのも毎度の事。晴れの日はまた会える日に、などと思えるのは既に9月に中標津便を予約しているからだろう(結局台風発生でこのツーリングは中止になり直前キャンセル)。
売店は17時閉店である。営業時間に間に合わなかったと思い、まず展望台訪問を優先させた。それなのに、鍵が開いていたからついドアの中に入っちゃったお行儀の悪い観光客に対し、閉店間際のソフトを食べさせていただけたのは大変有り難いことだった。




 ■
■



17:35民宿地平線着。犬の散歩に出かけていた石川さんが、ちょうど戻って来たところだった。石川さん、こちらの行動パターンを読み切っている。

 ■
■
一言で言うと、今回も抜群に楽しい根釧台地202kmコースだった。5度目にしてますます全く飽きることが無く、逆にコースに詰め込まれた含蓄がより一杯感じられている。中標津・標津・別海・浜中・厚岸、再び別海・標茶・そして中標津。各エリアの特徴がそのままコースの起承転結になっていて、各パートに少しも無駄が無く大変バランス良く根釧台地の総まとめになっている。しかも、一見1日中牧草地のアップダウンだというのに、全く飽きることが無い。それは根釧台地という素材の良さ以上に、石川さんの根釧台地愛のなせる技としか言いようが無い。
そして今にして思えば、このコースが2年間の北海道ツーリングのブランクが埋めてくれたような気がする。
熊は出なかった旨報告した。「良かったですね。今年は熊が多いんですよ」とのこと。熊についての恐怖の事実を、この時点では私はまだ知らない。
明日は例によって弟子屈札友内の鱒やまで行けばいい。天気予報は中標津で午前中雨、弟子屈で18時以降に雨なのだが、SCWで見ると根釧台地ほぼ全域の弱い雨は10時まで。11時以降は根釧台地北部でキレイに晴れ始め、その後弟子屈も含め雨は降らないとのこと。明後日は晴れ時々曇りである。
明後日はどうも津別峠とチミケップ湖を問題無く狙えそうだ。それなら、明日は無理して雨中ツーリングなどしない方が良い。お昼に出発してストレートに弟子屈に向かえば、15時前には弟子屈に着けるだろう。
朝の天気が雨なら、10時まで天気を見ながら宿で籠城させていただくことにした。

記 2022/10/16
#2-2へ進む #2-1へ戻る 北海道Tour22 indexへ 北海道Tour indexへ 自転車ツーリングの記録へ Topへ