

開陽→(道道150他)養老牛→(道道505他)計根別
(以上#2-1)
(以下#2-2)
→(町道・道道362他)矢臼別→(道道928)茶内原野
→(町道)中円朱別→(道道123)東円朱別
→(農道)大和→(道道988)姉別原野
(以上#2-2)
(以下#2-3)
→(道道988)恵茶人→(道道142)榊町→(道道123霧多布)
(以上#2-3)
(以下#2-4)
→(道道123他)厚岸
174km

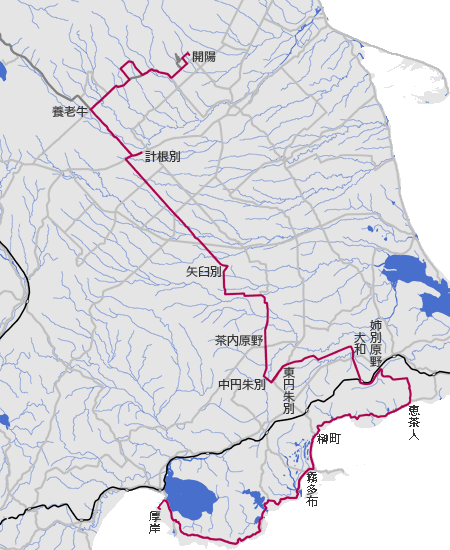
目が覚めると4時半、起きねば。さすがに2日目、まだ目覚まし無しで4時起床の身体にはなっていない。もう明るくなっている窓の外を見上げると、空の青い色が見えた。やった、晴れだ!すぐ準備して出発せねば。
と思って荷物をまとめ、外へ出てみると、窓が向いていた東方面は晴れだが、雲が出始めていた。東方面はどうかというと、すぐに降る心配は無さそうなぐらいの高さの雲が空一杯に拡がっている。ありがちなパターンなのだった。そしてその雲が空の中を西方面から東方面にけっこう高速で動いていた。天気は早くも晴れから曇りに変わりつつあった。


5:40、民宿地平線発。
カラマツの森に建つ宿から、森の中を少しだけ通って道に出てみると、さっき森の中から見えた以上に行く手の西側は雲が垂れ込めている。



それでもダメ元で町道北19へ出てみた。果たして開陽台方面の小山が、ベレー帽を被ったみたいに雲に覆われていた。今日の天気予報は晴れのち曇り。もう2時間もすると雲が切れ始めるような気もしないでもないが、まだしばらく展望は全く期待できない。仕方無い、昨日開陽台を楽しめたのだ。今回の開陽台はこれにて終了である。



開陽台の代わりというか、昨日も立ち寄ったダートの撮影ポイントに立ち寄ってから俣落へ。



昨日来た道道150を逆行し、北進の坂を登り切って山裾の台地へ乗り上げると、行く手の空の雲はますます厚い。



牧草地とカラマツの続く道は楽しく、緑の牧草地は鮮やかだが、まあこういう状況で晴れるとすると、だいたい9時から10時ぐらい。どう考えてもこの道から分岐する養老牛まで1時間強ぐらいなので、今回青空のこの道を通るのはちょっと絶望的だ。



昨日写真を撮りまくっておいて良かったが、まあ曇りなら曇りの景色を楽しめばいい。これも根釧台地の典型的な夏の景色なのだ。この道に来て、この道をのんびり走れていることが大切なのだ。▼動画51秒



途中で高峯方面へ分岐してみる。根釧台地の一番山裾のこの道道150だが、途中で更に山裾を登って戻る道を地図で見てちょっと気になっていたのだ。この道、何年か前まで使っていた地図だとまだあやしそうな細道で書いてあったのでノーマークだったのが、いつのまにか舗装拡幅されているようで、平成12年改定の地図ではちゃんとした太い道として描かれている。▼動画1分31秒



カラマツの防風林に沿った緩い登りへ踏み込んでみると、当たり前のことだがいつもの道道150の景色と比べて知床の山々が近づいてきた。そんな場所にも道ができるぐらいなので牧場があり、山裾の起伏のある空間に牧草地の開けた景色がダイナミクスを付けていて、新鮮だ。



少し時間に余裕があるとこういう寄り道ができるのである。新しく通る道がだいたい景色がいいこの辺り、今後もあまりタイトな行程を組まないようにしたい。▼動画41秒



昨日も通った道道150に戻り西へ向かうと、牧草地の上にはやはり次第に雲が広がって、いや、垂れ込めてきた。時々水滴も感じる。何だかちょっと雲行きが怪しい。▼旭新養老牛にて 展望260°(Quicktime VR) 画像上でマウスをドラッグしてください

振り向くと青空も見えるのだが、昨日暑かった内陸方面から雲が押し寄せてきているという雰囲気だ。何とか雨にだけはならないで欲しい。





7:00、養老牛着。昨日清里峠から中標津方面に方向を変えたここで西行きは一段落、今度はしばらく道道505で南下、太平洋岸も近い浜中町円朱別まで根釧台地内陸部が続く。一段落というか、何だか開陽まで行って帰ってきたような形になったが、未済のそれっぽい道を探したらこうなったのである。


養老牛から浜中方面へ向かうのは実は初めてで、根釧台地北部から南部へ向かうのに、対角線を使う過去一番距離が長いコースでもある。それだけに今日はこれから早めに浜中へ行ってしまえると後が楽だし、その後折り返しを粘って、去年行けなかった恵茶人海岸には是非とも行きたい。幸い今日はこの後晴れる予定なのだ。あまりぎりぎりの見込みをしない方が気持ちも楽だし、何より判断ミスの可能性そのものが少ない。
1986年以来訪れているこの道で印象的なこの養老牛の交差点。もうずいぶん前から店が開いていることが希なこの店、正面の看板は「ながかわ商店」、側面の看板は「伊原商店」とということで正体不明だった。。今回、よく眺めてみた集落案内板で、初めて「ながかわ商店」であることがわかった。「中川」じゃなくて「長川」なのだった。店が閉まっているので自販機の飲み物が買えるだけだが、宿で作ってもらったおにぎりは食べることができる。
7:20、養老牛発。



道道505は一直線の緩い緩い下り道。どんより雲の下にカラマツ林、牧草地、そしてまた林と、似たような景色が入れ替わり立ち替わり延々と続く。まあそんなことは地図を見て予想は付いていたはずだ。



どんより雲の下、いや、丘陵に覆い被さっている低い雲の中、緩い下りに乗じて踏み込むわけでもなく下りなりに、ひたすらそんな景色の中をだらだら下っていると、時々水滴も感じ始めた。水滴は微妙にぱらっと来てからすぐ止むが、さすがにちょっと先行き不安になってきた。


正面遠くに車が時々行き交う道が現れたと思っていると、次第に近づいてみれば見覚えのある道道13だった。牧草地と防風林のグリッドを斜めに突っ切ってゆく道で、グリッド通りに一直線のこちらの道とは、それだけで表情はやや異なる。
ここまで来たら、とりあえず計根別でおにぎりを仕入れておかないといけない。早朝の宿で食べた、昨日残りのおにぎり分のエネルギーも早くも切れてきたようで、腹が空き始めていた。

8:00、計根別着。確か町の反対側の外れにセブンイレブンがあったはずだが、幸い記憶に無いセイコーマートを発見。サラダにおにぎり、100%オレンジジュース、仕上げにヨーグルトと、セイコーマートの歌のように集中的に朝食とする。
8:30、計根別発。またさっきの道道505・13の交差点から少しスライド、町道で南下を継続だ。まだまだ南に行かないといけない。






▼動画1分11秒牧草地と防風林が続く景色は相変わらずだが、これまでの一方的な下りから谷間を横断するアップダウンが増えてきた。



道の方向は変わらないが、長く続いた知床山地の裾が終わって地形の方向が変わってきたのだ。



同じような景色が続いているようではあるが、こう言うところに少しづつ進んでいることを実感できる。



いや、もう養老牛からもう20km以上ぐらい下ってきているのだ。






上春別の外れで国道272と交差、ここもそのまま横断し、更に2回のアップダウンの後国道243と交差。






次はいよいよ矢臼別から円朱別、町道何本かを乗り換えながら自衛隊矢臼別演習場を回り込んで海岸部を目指す。






相変わらずどんよりの低く濃い雲が頭上を覆っていて、時々ぱらっと雨が降ってきたりもする。▼動画32秒






牧草地と防風林の丘陵地帯の中で道は何度か方向を変えながら、自衛隊矢臼別演習場を回り込むように迂回してゆく。▼動画2分38秒



演習場というと何か物々しい印象で、実際に放談大戸が聞こえてくるときもあるこの矢臼別演習場だが、地域にとっては除雪その他防災上での頼れる存在だ。



地形は山裾の中標津地形から、完全に丘陵の別海地形に変わりつつある。



町道の分岐を選び、道を移ると、大きい線形で丘から丘へとアップダウンが続く。丘の上からは周囲の展望が一気に拡がって感動的だ。




既知の上風連方面との2択で入り込んだ道道928は未済の道。未済とは言え、まあこの広く同じような地形の根釧台地、場所が違っても景色のニュアンスが変わるというものではない。丘と谷のアップダウンに、丘の上なら丘の上で緩い起伏に、牧草地と防風林が相変わらず雲の下に続いていた。



11:30、中円朱別着。もう少し南下して国道44と根室本線を越えてしまえば、太平洋岸台地エリアに入るところまで来た。この太平洋側というのは私的区分のようなもので、国道と鉄道で区分される大雑把なエリア分けではあるのだが、経験上はここで天気・気温・風向きが面白いようにがらっと変わることがあるのだ。とにかくそういうわけで、いよいよ太平洋岸に順調に到着できそうなのだった。
それなら恵茶人の海岸へ足を向けることを検討してみよう。恵茶人は東南の方角、今日の終着地の厚岸は西南西の方角。つまり逆方向への回り道になるが、時間的に訪問自体は全然大丈夫そうだ。
それではどういうコースにするか。このまま直進を続けても問題は無いが、いつも通る道道より、静かで鄙びた町道を経由するチャンスだ。それにここから真っ直ぐ南下する道は、何だかここ何年か時々通っている気もする。ここは今日のチャンスを生かし、道道123を少し東へ向かってから国道44北側の未踏エリア、北部・大和方面を横断して姉別へ南下する農道に入り込むことにした。



道道123自体は過去何度か通っている。程良いアップダウンと程良く変わる典型的な浜中内陸部の景色がとても楽しい道だ。丘の上ではところどころでこの辺り独特の地平線まで見え、途中の東円朱別には給水ポイントの小学校もある。



その東円朱別の分岐で本題の北部方面の農道へ。▼動画2分32秒



今風幅広道道な道道123と較べると、やや幅が狭く舗装もどこか平滑度が低いような頼りないような気がするが、何より路上が静かで落ち着いているのがいい。



道は丘の上を北部へ向かう。牧草地、一直線の道、牧草地と防風林が安定した地形にしばらく続く。



北部までの東向き区間ではけっこう横風っぽかった風向きは、道の方向が大和・姉別方面の南向きになると急に強向かい風に変わった。それに、牧草ロールの農業トラックの通過で、乾いた土埃と藁の破片が煙いし目に埃が入ったりする。



身体のつらさとともに、急に強力な眠気も感じ始めてきた。もうそろそろ12時、普段はお昼寝タイムのこの時間である。旅程のまだ2日目、まだ普段の生活習慣が残っているのか、それとも昨日寝るのがちょっと遅かったからか。何しろもう意識不明寸前である。



等と思っていると、空が明るくなったと思ったら急に雲が切れ、青い空が見え始め、辺りも明るくなってきた。ここまでかなりきわどい状態もあったが、何とようやく晴れてきてくれたのである。


12:25、姉別着。記憶通りにここの駅は無人駅ながら駅舎と万屋があった。とりあえずこの中へ緊急避難、とにかく眠い!
待合室の駅前側とホーム側の両方の引き戸を開けっ放しにすると、涼しい風が通り抜けてゆく。日差しは厳しいが、気温自体はそう高くないのだ。誰もやってこない無人駅の待合室に夏の風。なんだかとても懐かしい夏の旅の気分で目を閉じ、しばし居眠りへ突入。
目覚めると6〜7分過ぎていただけだったが、一気に頭がすっきりしているのもいつも通り。ついでにここで軽くおにぎりも済ませてしまう。
12:50、姉別発。この間に雲はますます消えて青空が一気に拡がり、完全に晴れてしまった。



そうなると、さっきまでの曇りとは打って変わって気温が上がり始めるのは毎度のこと。



今までの向かい風も進行方向が変わると微妙に横風から追い風に変わり、一気に明るい草原の快調な、夏らしいツーリングと胸を張って言える状態になってしまった。さっき一寝入りして頭がすっきりしているのも大きい。



姉別の明るい牧草地を、根室本線沿いに更に東に進む。 ▼姉別原野にて 展望280°(Quicktime VR) 画像上でマウスをドラッグしてください




まぶしい半逆光の青空には白い雲、輝くような草色には白いビニールに包まれた牧草ロールが点々とばらまかれていて、鮮やかな色彩と唐突なテクスチュアがまるでモダンアートのようだ。



これから向かう海岸方面は、何だか空の下の方に少し色の濃い雲が溜まっている。それは何だか露骨に湿った色のようでもある。でもまあ、去年もこの辺りでこんな空を眺めていて、しばらく走った落石の海岸では太平洋の海岸は晴れだった。同じ場所での同じ景色、多分今日も同じパターンだろう。



道道988で根室本線から離れ、牧草地の台地上を少しくねくねと更に西へ。向かい風と追い風に一喜一憂しながら台地の隅で道は唐突に方向を変え、海岸の低木林に突入。間もなくダートが始まった。毎度のことだが、高い茂みと熊出没注意の看板がちょっとブキミではある。



この辺りから、いつの間にか空は再び曇り始めていた。その曇り度合いがけっこうどんよりである。

気温も明らかにさっきより下がっている。まあこの辺りの海岸近くは夏でも内陸より気温が低いのだが、この感じだと今日の海岸は曇りなのかもしれない。


その予想通りに、道が下りはじめてすぐ海が見えると、太平洋、波の打ち寄せる砂浜、近くの草原に遠くの陸地、景色のすべてが灰色〜薄茶のトーンの中である。やはり海岸沿いはどんよりの曇りなのだった。



恵茶人からは海岸の道道142、通称太平洋シーサイドラインへ。


貰人までは海岸沿いの1本道。広々と開けた太平洋とやはり開けた海岸部の低地、その奥に迫る根釧台地台地の縁を眺めながらの、晴れていれば気分のいい道だ。牧草地には牛や馬も多い。しかし今日はどんよりの曇り、薄暗い世界である。

雲は厚いがそう低くはなく、今にも雲が落ちてくる、という雰囲気は無い。しかし、しょっちゅう顔に水滴が当たる。というより、水滴が路面をしっとり濡らしてにわか雨直前ぐらいで降りが続かない、というぐらいが続いているようだ。



去年、花咲港へ向かう行程の途中、さっきみたいな晴天だったのに、眠気やら強向かい風やら安全側見込みやらでこの恵茶人海岸の経由を断念した。後で地図を見たらそんなに大回りでもなく、その時はだいぶ後悔したものだった。しかし今、その後悔は完全に消えた。あの時こちらへ向かっても多分こんな感じだったのだ。何しろ落石は30kmも先なのだし、同じ太平洋岸とは言え、いや、天気の変わりやすいこの道東太平洋岸、天気が全然違って何の不思議も無い。






貰人の先は羨古丹、奔幌戸、幌戸と、道道142は緩やかな曲線を上下左右に描き、丘へ登って海岸の海岸の小さな漁村へ下って、集落の向こうですぐまた登り返す。



丘は一つ3、40mから最大80mと、高さとしてはまあ山あり谷有りぐらい。しかし、海岸の岸壁に登ってすぐ降りるせいか斜度は厳しめ、と言うより連続アップダウンがしつこくくどく、気持ちが疲れる。 ▼羨古丹にて 展望220°(Quicktime VR) 画像上でマウスをドラッグしてください

幅が広い道を通すための法面や切り通しは、たとえ植裁があっても味気無く、面白いものではない。とりあえず前へ進むに、一つ終わってもすぐ現れる丘を、えっちらおっちら一つ一つこなし続けるしかない。前回の2004年は身体そのものがけっこう疲れていたせいでなかなかしんどい道だと思ったが、いや、そうでなくてもなかなかしんどい。




でもまあそれだけにというか、丘の上から海岸に急降下する景色はなかなか悪くない。楽しみどころをわかってしまえば、粛々とそれを楽しめばいい。ここまでの内陸の道と違い、とりあえず漁村には民家が集まっているのも、自販機のある集落が少なくないのも安心感がある。




後静の少し内陸を経由し、丘の奥でややくねくねと登ったり下ったりするこの区間最大級のしぶといアップダウンは、手持ちの地図に載っていない。






そろそろ終わるか、こんなところで曲がったら陸地の奥の方向だよ、もう一発登り返しなのか、などと一喜一憂しながらようやく榊町の海岸へ。

最後の丘を抜ける榊町トンネルがよく見える砂浜、その波打ち際に面した開けた景色は、ここまで見ることが無かった目新しい雰囲気だ。例え恵茶人と言えども砂浜の部分がもう少し広いので、ほんの短いこの区間、しつこかったアップダウンの後の、海に沿って走る気分一杯の楽しい道だ。海猫もフェンスに佇んでいる。▼動画21秒


榊町トンネルの向こうで浜中からの道に合流。午前中養老牛からの南下で時間を食ってしまったら、ここで道道142に合流していたはず。例えしつこいアップダウンでも、終わってみれば来れてよかった、という気持ちしか残っていない。



その先霧多布まで10kmぐらい、しばらく海岸の平坦な道が続く。



道の両側に民家が点在できるぐらいの、砂浜から少し内陸に道は続く。広々と拡がる霧多布湿原の端っこ、海側も陸側も景色の変化は乏しい。おまけにこの道、いつも強追い風か強向かい風か、とにかく風が強烈なのだ。今日の所は強の範囲の弱ぐらいの向かい風。まあ強の弱なだけ良しとせねば。



14:55、霧多布着。霧多布半島への入口を少し過ぎた道沿い、記憶通りにあったセイコーマートで小休止とする。過去通ったことがある道の過去立ち寄ったセイコーマート。通る道が同じなら立ち寄るセイコーマートも同じで、もはやセイコーマートはツーリングの道の景色と同じく、ツーリングに欠かせないものと言える。
というより、朝の計根別からここまで初めてのセイコーマート。内陸部の町道や農道ばかり通ってきたので当たり前だが、勢い補給も集中的になり、時間が掛かる。
もう15時過ぎ、出発を15時半とすると、ここから厚岸まで登りと写真込みで、粛々と進んでまあ2時間半ぐらいだろう。宿の夕食時刻ぎりぎりである。
霧多布を過ぎ、茶内方面への交差点を過ぎると、1999年以来10年振りの道だ。



まずは霧多布の湿原が終わる琵琶瀬から、琵琶瀬高台への登りが始まる。

丘の上から見下ろす湿原が霧多布の町の広がりに続いて行く様は見事だが、いかんせん水滴が雨になり掛けている。先を急ごう。 ▼琵琶瀬高台にて 展望240°(Quicktime VR) 画像上でマウスをドラッグしてください






渡散布、火散布とさっきのようなアップダウンの後、藻散布への丘にはこの道数少ないトンネルが設けられている。ここにトンネルが無いと、何だかかなり急な坂になってしまうような気がする。さっきの榊町トンネルも何だかそんな感じだった。多分やってられないのでいち早くトンネルが造られたのだろう。






その短いトンネルを抜けると、藻散布の集落と藻散布沼が登場。狭い谷間の海側と陸側に続く、海と沼の開けた空間が独特の雰囲気だ。雰囲気だけではなく、ここは1986年の初めての北海道ツーリングで、とても印象に残った場所だった。


その日は、阿寒湖の向こうの野中温泉から、この藻散布に建っていた旅人宿「白鳥の宿」までの行程だった。標茶から先の根釧台地で、所々で地平線が拡がる景色に圧倒されつつ、上腕に日焼けの水膨れができたほど鋭い日差しに意識が遠くなるほどだった。ところが、厚岸の海岸に降りた途端に冷たい霧の中に突入。今度はトレーナーに上着を着ていないと寒くて歯がガチガチ鳴る低温で身体が縮んだところに、道道142で海岸台地の登りが登場。おまけにこの道道142がダートから歩道に舗装中で、随所の深砂利ダートでもうへとへと。濃い霧にくねくねカーブでどこを走っているのか全くわからない状態で、霧の中から唐突に現れた沼地がこの藻散布だった。
道の脇の看板を頼りに、何とか宿に辿り着いた時点でもう19時過ぎ。宿の前で荷物を下ろしていると、脚、腕、露出した肌にアブラムシみたいな細かい虫がいっぱいたかってきた。アブラムシだと思ってしばらく放置していたが、あんまりたかってくるので払うと、手が真っ赤っかになってしまった。血だった。虫は北海道独特の、網戸が役に立たないほどの微細吸血昆虫ヌカカだったのだ。
怖れおののきながら宿に入ると、何と食堂には真夏なのにストーブが焚かれていた。寒いのにようやく納得。ここはそういう場所なのだと思い知った。その食堂で食べた花咲ガニと毛ガニの合わせ味噌汁「花毛汁」の美味しさが、その日最後の強印象で、まあとにかく道東の驚異にやられっぱなしの道東初日だった。
白鳥の宿自体はいつの間にか宿を畳んでしまったようだったが、建物自体は前回訪問の1999年、まだ残っていた。今回も道道の橋の上から、藻散布沼のほとりに黄色くペンキが塗られた小さな番屋をすぐ見つけることができた。1986年から20年後以上、前回からでも11年。ちらっと眺めただけの再開だが、思い出すことは多い。



藻散布からの登りは、何と全面的にルートが変更されていて、地図とは全く違う経路で藻散布沼沿いに丘の側面を大きなカーブを描いて台地上に乗り上げる。



登った台地では、鬱蒼と濃く低めの不気味な雑木林が続く。熊出没注意の看板が時々立っていて、さらに不気味さを盛り上げる。



その表情は、この道の恵茶人海岸の更に東、根室市内の初田牛・落石間の森ととても似ている。違うのは向こうは道が延々とほぼ一直線、こちらはくねくねとやや迷走気味であることだ。



時々道が台地の際に近づくと、森が切れて辺りが笹原になり、見下ろす谷間に太平洋が登場する。▼動画35秒



所々に展望駐車場も設けられていて、青空の日の景色を想像してしまうが、いかんせん今日は軽くぱらついたり止んだりの冴えない天気。海もなんだかとりつく島のない鉛色なのだった。






海縁の道はまた内陸へ戻り、鬱蒼とした森が再開する。



時々鎖ゲート閉鎖中のダート林道入口が現れる。それらは間違いなく熊注意系の道で、なかなかこの道道142から更にその内側に踏み込みにくい原因になっている。






その林道の名前の地名で、自分の位置が少しずつ西へ進んでいることを理解できるのは少しありがたい。



標高60〜80mぐらいで推移していた道は、軽いアップダウンを繰り返しつつ高度を上げ、最後に130m弱の通信塔脇まで登ってからおもむろに下りが開始。






床丹からの道道955と合流すると谷間が拡がって、藻散布からここまで20数km登場することの無かった民家が登場。すぐに目の前に厚岸湾が現れた。






厚岸湾と陸側の小山に挟まれた狭い浜辺に続く漁村では、道の脇に建つ家々が新しめで、活気がある。全国に有名な蠣をはじめ、海の幸が豊かな土地なのだろう。そろそろ夕食の煮物らしい香りが路上にまで漂っている。自分の空腹にも気が付いた。



厚岸市街から1本裏手の道の厚岸港へ、その外海側に目指す厚岸愛冠YHがあった。17:50、厚岸愛冠YH着。


厚岸愛冠YHに泊まるのは今回初めてだ。厚岸への宿泊自体も初めてである。前述の1986年の低温ショックが強烈な印象で、もっと道東の奥へ訪れるようになり何が起きてもあまり驚かなくなったても、厚岸という場所にあまり根拠の無い警戒心が残っていた。泊まるときには腰を据えたい、と。このため、毎回の計画では経由はしてもなかなか泊まるまでには至らなかった。
まあ一方で太平洋岸・内陸、そして東側・西側相互間の移動には便利な場所ではあるし、釧路・根室間の最大の町で利用価値は非常に高い。というわけで、今回はごく自然に厚岸に泊まることにしたのだった。
その初めての厚岸愛冠YHは、遠藤旅館という旅館併設のYHである。旅館併設のYHの場合、建物は旅館エリアとYHエリアが分かれている場合が多い。今回はやや古めの建物だが、旅館とYHは完全に一体化していて、布団敷きと浴衣のサービスが無いだけのようだ。部屋も古めでいかにも商人宿そのもので素っ気ないが、鍵付き完全個室なところまで旅館と一緒、これは非常にポイントが高い。

ところが、それ以上に度肝を抜かれたのが食事だった。
何と作り分けるのが面倒くさいからか、旅館と全く同じ内容の食事が出てきたのだ。さっき漁村を眺めて腹を減らしたその厚岸の海産物が、色とりどり&ボリューム満点なのである。大きな蠣が貝殻付きで3個、これとは別に蠣の鍋が付き、もう一つ目玉が今朝取れたばかりのサンマ煮付け、刺身、そして甘エビ。その他鶏肉の大きな焼き物、野菜もたっぷり、と後は一緒くたにしてしまうが、おつゆに至るまでテーブルに乗り切らない。
旅館で出たとしても過去最上級の食事、それがYHで出てきたのである。蠣はさすが噂の厚岸、と言い切れる素晴らしさだったが、それ以上に良かったのがサンマ。魚好きの私は、サンマは特に大好きなのだが、煮付けも刺身も脂が乗っている以上に豊かとしか言いようが無い、新鮮というのも少し違う、食べたことの無い味わいなのである。この「豊かとしか言いようのない味わい」、昨年の羅臼でもいろいろな海の幸で感じることができたが、やっぱり道東の海産物はいい。良すぎである。
私的過去YH最高夕食は、幌加内で何年間かYHだったころの朱鞠内そばの花YHということになっていたが、これを軽く更新してしまう凄い食事なのだった。
記 2009/8/29