頸城の秋06 #1-1
2006/11/3 十日町→宇津俣
十日町→(県道75・国道253他)北鎧坂→(県道49)高島
→(県道528)名ヶ山→(県道427)海老
(以下#1-2)
90km

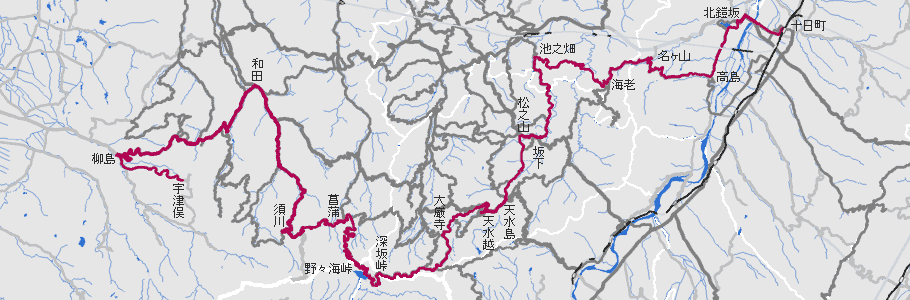
頸城の秋06 #1-1
|

|
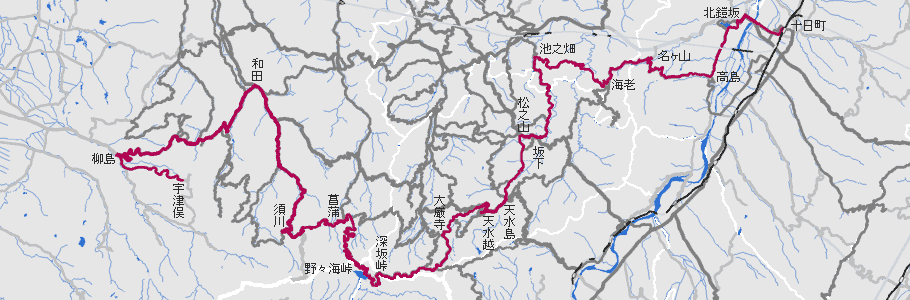
|
|
ほくほく線連絡が始発から2番目の新幹線になって、もうだいぶ経つ。越後湯沢での連絡は特急はくたかと普通列車の2本立て、先発の乗り継ぎで慌ただしいはくたかの乗客をのんびり眺めて、普通列車に乗り込んで居眠りを開始。目覚める頃には十日町到着、楽々アプローチだ。
寝ぼけ眼で時々目を開けると、魚沼丘陵はまだ朝の霞で真っ白だったが、トンネルを抜けた十日町側では、もはや空には雲一つ無い。あらを捜すと遠景がやや靄っぽいが、ここ数年では間違いなく最高級の晴れっぷりだ。こういう日は気温も暖かだろう。
駅から少し離れたコンビニで出発前に補給。町中だと言うのにトンボの姿も見られる暖かな陽差しに、ついつい何と無く長居してしまい、9:45、十日町発。

|

|

|
東頚城丘陵を直江津へ北越急行ほくほく線に付かず離れずの国道253、何と「ほくほく街道」という名前が付いてしまったようで、そんな看板が立っているのにびっくり。その国道253で信濃川を渡り、十日町対岸の河岸段丘へ。



少しの間台地上の農村の中の田舎道が続く。北鐙坂、南鐙坂と農家や万屋、酒屋に農協が現れ、集落が切れると田んぼの中に道が続く。手前の刈り取り後の株だけが並んだ田んぼと、奥の魚沼丘陵手前まで広がる十日町の平野部。その間が幅が広く河岸段丘の高度差がある信濃川なので、手前から魚沼丘陵までずっと視界が続いてゆく。更にこの青空。空気もちょっと涼しいぐらいの極上の快適さ、単純に流しているだけで有頂天になってしまう。



高島からは県道528へ分岐。道の雰囲気が急に荒々しくなり、いよいよ東頚城丘陵に取り付いたことを実感させる。とはいえ、崩落復旧や地滑り防止工事でこの道も以前よりだいぶ拡幅され、その表情は和らいだとは思う。
切り立った谷間の森の細道からは、谷底の棚田に対岸の山の木々、地層も露な岩肌が見える。山肌の広葉樹は、真っ赤だったり色付き始めだったりまだ青々としていたりして、やや紅葉の見頃には早いようだ。その広葉樹と、所々ににょきにょき立つ濃緑の杉。この辺りの景色は、つくづく棚田と杉と雑木林が雰囲気を作っていると思う。



間もなくカーブの向こうに民家が現れ、鉢に到着。急斜面に大きな農家が寄り集まる、この辺りではやや大きめの集落だ。商店もあり、夏だとここで早くも冷たい飲み物が欲しくなるので、有り難い印象が強い。



今回この鉢では、そう広くない県道528が集落の中で崩落しているようだ。下って登っての迂回看板に従い、大人しく下って登っての回り道へ。今まで通ったことの無い道なので、これでもいいのだ、等と自分で納得しながら集落上手の中手トンネルへ。



民家の狭間、山肌に穿たれた中手トンネル。小さな入口は、近くへ寄っても自転車で通り抜けられるか心配なぐらい小さく狭い。しかし、入ってみるとその中はそこまで狭いことはない。照明も付いていて、安心して通ることができる。



それでも狭い入口に「突入」という言葉が思い浮かび、そう長くない向こう川の出口では「脱出」という言葉が思い浮かぶ。トンネル断面なりに小さなスノーシェッドの向こうは明るい秋晴れの谷間の田んぼで、すぐに集落の中に登りが再開する。






中手の民家に棚田、畑と杉とススキの穂の道をくねくね登り、ピークを越えると広葉樹と民家に棚田の谷間、中平へくねくね急降下。▼動画2分15秒

|

|

|
さっき越えた丘を見上げると、その丘も辺りも、赤に薄黄色に緑の広葉樹で覆い尽くされている。道ばたには柿の実も目立つ。何も全山目一杯真っ赤っかじゃなくても、これだけ色とりどりの秋に出会えれば上出来だろう。それもこれもこのお天気ならでは。






中平から谷間を登り返した道は国道253手前の名ヶ山で折り返し、薬師峠へ向かう国道253の旧道に合流。



峠でもないのに集落間の道が登って下ってばかりのこの辺りにしては、薬師峠への登りはかなり緩めだ。

|

|

|

|

|
その旧国道253から分岐すると、別れた旧国道253はひょいと丘の縁を越えて薬師峠へ、こっちは更に谷間を遡る1本道として海老へ向かう。



深く落ち込んだ谷に面する幅3mちょっとの細道。その縁にはガードレールなど無く、4mおきぐらいに道の縁を示すポールが頼り無く立っているだけだ。周りが木に囲まれている内は安心だが、木が切れると、見下ろす紅葉の眺めと、足下に落ち込む谷間の恐怖との間で苦しむことになる。

谷の一番奥の縁をひょいと乗り越えると、海老の上手である。

|

|

|
ここには展望台というか、いや、それほど整備されていない、程良く草生した広場がある。いつもここから東川、海老、下山から国道253辺りまでの谷間の見晴らしが拡がるので、紅葉と天気に恵まれた今回、ここへ来るのが楽しみでしょうが無かった。

果たして広場からは、赤っぽく色付いた丘陵の波が、青空の下遠くへどんどん青い影になって続いてゆく広がりが一望にできた。南側の一番遠くは、やや薄い山並みのシルエットで視界が止まっている。あと3時間ぐらいであそこまで登ってしまうのだ。

記 2006/11/19